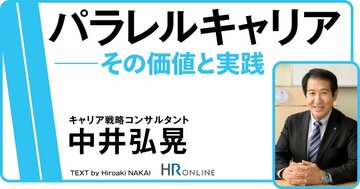教員と学生にとって、インターンシップの存在は…
同志社大学は、いまから22年前の2003年度に、学際科目「キャリア形成とインターンシップ」を新設し、企業における学生のインターンシップを正課として単位認定した。当時、浦坂教授は、「機会があれば、どんな型であれ、(インターンシップに)参加してみるといい。希望業種であってもなくても、大企業でも中小企業でも、親切にしてもらえても邪険にされても、満足しても落ち込んでも、それはすべて思いがけない自分と出会うチャンスである」と、学生にメッセージを届けている(*2)。
*2 「インターンシップに見る企業の姿勢と学生の想い」 2003年度文学部就職情報(春号)より
浦坂 私がインターンシップについてそう書いたのは20年以上も前で、まだ、インターンシップの実施自体が珍しく、正課科目にすることはかなり先進的な試みでした。現在は、インターンシップが就活の手段として認知され、特に3年生の夏に学生がインターンシップに行くことは当たり前になりました。本採用の面接だけで学生の適性や力量、人柄などを見抜くのは難しいので、グループワークなどで時間をかけて、企業側が学生を評価するのはいいことだと思いますし、学生側もその企業で働く姿をより具体的にイメージできると思います。
企業も学生も、インターンシップは「使い方次第」でその善し悪しが決まると、浦坂教授は言葉を続ける。
浦坂 低学年でもインターンシップに行くことはありますし、内々定を3年生の秋に出す企業も珍しくありません。私が教えている学生も、だいたい4年生になる前には内々定を得ているくらいに就活の動きが早くなっているので、学生はさまざまなインターンシップに時期を問わず参加しています。かつては4年生のゼミが就活で成立しなくなると言われましたが、いまはどの学年でも「インターンシップに行くので授業を欠席します」となります。就活も大切ですが、本来大学で身につけるべきこと、やるべきことが疎かになってしまうことを、私は懸念しています。特に、3年生は最も学業を深められる時期なので、インターンシップで授業をしょっちゅう欠席されると、こちらも落ち着きません。「ガクチカ」がインターンシップや就活になってしまうのは本末転倒ですし、誰にとっても望ましいことではないと思います。
そうした状況において、浦坂教授は、新卒の人材を受け入れたい企業は、「(学生が)豊かに実ることを信じて待つ」姿勢も必要だと説く。
浦坂 企業は優秀な人材を確保したいがために、どうしても早め早めに「青田買い」をするのでしょうが、そのために、大学でやるべきことが疎かになって、本質的な力が身についていない新人を受け入れることになってもいいとは思っていないはずです。未熟なまま学生たちを社会に送り出しても、入社後にしっかり育ててくれるのであればいいのですが、その覚悟がないのであれば、もっと、大学教育や学生たちの学びを信じて、尊重してほしいと強く思います。「青田」の1年後、2年後の成長は計り知れません。大学という場でしか経験できないことを存分にやり尽くし、豊かに実った後の学生たちの姿を見て、評価していただきたい。この先も少子高齢化はいっそう進むでしょうから、どうすれば、貴重な若い人材を守り、育てていけるのかということを、自社の利益や都合を優先するのではなく、社会全体で考えていただきたいです。学期中の平日に学生を呼び出すことを控えてもらうだけでも随分違うと思います。