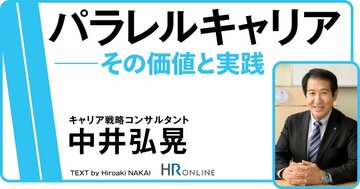自分の将来や生き方にかかわる、身近な、「働くこと」
ユニークな学科として知られる、同志社大学社会学部産業関係学科。学科のスローガンは、「“働く”を学ぼう」――「産業関係」は英語で言えば、Industrial Relationsで、労使関係・雇用関係を学びながら、教員と学生は「働くこと」をさまざまな角度から研究している。籍を置く学生は、たとえ、第一志望での入学でなくても、4年間の学びで、「働くこと」の意義や価値を見出し、各界で活躍する人材として巣立っていく。
浦坂 大学の入り口は広くていいと私は思っています。ですから、産業関係学科で何を学ぶのかをよく理解せずに入学してきても構いません。ただ、卒業する時に、「ここで学んでよかった」と実感してもらいたいですし、そうなるように努力してほしいですね。そのためには、「いまここで、できるベストを尽くしてみる」というマインドセットが重要です。同志社大学は総合大学ですから、他学部の授業も受講できますし、産業関係学科での学びがどうしても合わなければ、転学部や転学科もできます。大学には、多様なリソースや学びの機会があるので、それを十二分に活用して模索すればいい。働くことへの向き合い方も同じだと思います。不本意な職場に配属されたから「辞めたい」ではなく、いまここで自分に何ができるのかを、まずは落ち着いて考えてみてください。
「Z世代の就業観-仕事のやりがいに着目して-」「カスハラ対応者の心理的負担から見るカスハラの要因と問題点」「主夫家庭の抱える葛藤について」……浦坂ゼミで学ぶ学生の卒業論文(*3)は、「働くこと」に関する多彩なものになっている。
*3 同志社大学社会学部産業関係学科 卒論賞ページより
浦坂 「働くこと」は、自分の将来や生き方に直結する、すごく身近なことなので、手はじめに自分の趣味や関心事から研究テーマを探してみることを勧めています。例えば、サッカーをずっとやってきた学生であれば「Jリーガーのセカンドキャリア」、アニメ好きな学生であれば「アニメーターの労働条件」など。これらのテーマは取り上げられることが実に多いのですが、それぞれの学生の問題意識によって分析の切り口が変わるのが面白いところです。また、趣味や関心事ではなく、自分自身の特性や就職に対する不安、皆と同じように就活することへの疑問などから、フリーランスで食べていけるのかを考察した学生もいました。一人ひとりの学生が胸の内に切実に抱えている問題意識に気づき、そこから内発的に導き出された研究テーマでなければ、長い時間をかけて掘り下げることなどできません。この論文を書くのが必然だった、あるいは、この論文を書けてよかったと、彼ら彼女らが納得して卒業を迎えられるように、私も伴走しています。