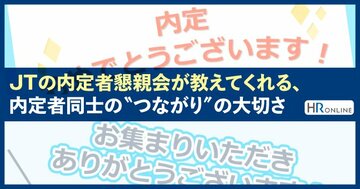福島宏之
LGBTQの理解促進――「となりの多様性 ちがいを知って、ちがいに寄り添う」ことの大切さを考える
さまざまな人があらゆる働き方をする社会――「個」「一人ひとり」「多様性」という言葉が、HR(ヒューマンリソース)の領域で目立つ時代になっている。フリーアドレスの職場も増えるなか、となりに座った人がどういう人なのか、新卒・中途採用で入社した人がどのような働きづらさを感じているのか……“他者の思いに気づき、考えを知ること”が、ハラスメントを生まないためにも、誰もが働きやすい環境をつくるためにも大切だ。「となりの多様性 ちがいを知って、ちがいに寄り添う」と題された、メガバンク合同主催イベントの様子を「HRオンライン」がレポートする。

マシンガンズ滝沢秀一さんが語る、 “ふたつの仕事”をずっと続ける理由
仕事は何のためにするのか? 「お金を得て、生活するため」と答える人が多いだろう。だから、お金を得るために、好きでもなく、得意でもない仕事に向き合っていくこともある。お笑いタレントの滝沢秀一さん(マシンガンズ)が収入のために始めたのはゴミ清掃の仕事――「働き始めて、すぐに辞めたい!と思いました」と当時を振り返るが、いまでは、使命感を持って、“お笑い”の仕事とともに、ゴミ清掃の仕事を続けている。新卒者(2026年4月入社予定者)向けの媒体「フレッシャーズ・コース2026」にも出演している滝沢さんに、“ふたつの仕事”を続ける理由を語ってもらった。

職場につくられた「子ども図書館」が、働くみんなを幸せにする理由
コロナ禍を経た、2020年代半ばのいま、人事・総務といったバックヤード系の業務は多忙を極めている。従業員の勤怠管理から福利厚生に至るまで、積み重なる案件に追われ、時間を効率的に使うことを余儀なくされながら、従業員の「働きやすい職場」づくりに腐心する人事・総務パーソンが多いようだ。そうしたなか、働く人の心と体を休める「リフレッシュルーム」に「子ども図書館」を設置した職場がある。弥生株式会社の大阪オフィス(大阪カスタマーセンター/大阪支社)だ。いま、なぜ、「子ども図書館」なのか? その企画・運営をおこなう森嶋綾子さん(人事本部・人事総務部)を訪ねた。
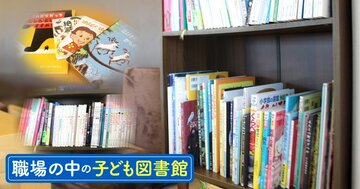
考え、迷い、また考え、また迷う――働き始めた新卒社会人に伝えたいこと
新卒者の就職活動における、早期化・長期化の傾向が強まり、多くの学生が、将来の就職先や仕事を意識して学業に向き合うなか、関西の総合大学に、雇用や労働について専門に学ぶ学科がある――同志社大学社会学部産業関係学科。「働くこと」をさまざまな角度から研究するユニークな学科として、企業や行政機関からも注目され、卒業生は人事企画部門をはじめ、さまざまなフィールドで活躍している。企業の入社内定者向け媒体「フレッシャーズ・コース2026」にも出演し、雇用や労働にかかわるテーマに取り組む浦坂純子教授(同志社大学社会学部産業関係学科)に、同志社大学・新町キャンパスで話を聞いた。

令和の時代に、“人を大切にして、地域に貢献する企業”が輝く理由
2030年での達成を目指すSDGs――そのゴール8「働きがいも経済成長も(Decent Work and Economic Growth)」、ゴール11「住み続けられるまちづくりを(Sustainable Cities and Communities)」を継続している企業がある。収益不動産の再生・売買事業、賃貸管理事業(プロパティマネジメント)を行う武蔵コーポレーション(さいたま市大宮区)だ。昨年(令和6年/2024年)には、埼玉ちゃれんじ企業経営者表彰で埼玉県知事賞を受賞するなど、地元にも欠かせない存在だ。“人を大切にして、地域に貢献する”ことを目指す企業は多いが、実現はなかなか難しい――同社を創業した大谷義武さん(代表取締役)に、その実現までの道のりと「住まいで人を笑顔に」する方法を聞いた。

人事部が自社に合ったIT人材を採用し、会社全体のITリテラシーを高める方法
経済産業省が2018年に「2025年の崖」という表現で、DX(デジタルトランスフォーメーション)の必要性を説いてから7年。コロナ禍で多くの企業のIT化は進んだものの、民間企業の最新調査によれば、DXに関して、「十分な成果が出ている」と答えた企業は10%程度にとどまっている。その理由のひとつに、各企業における、IT・DX人材の不足があるだろう。そもそも、IT人材とDXを行う者は異なるのか? なぜ、自社でエンジニアを含むIT人材を雇用する必要があるのか? DXを推進する企業は、どのような人を採用し、どう向き合っていけばよいのか? エンジニアとして社会人生活をスタートし、人材エージェントの大手で2000名以上のエンジニアの転職をサポート――その後、起業し、現在は、HRコンサルティングサービスなどを展開している、株式会社レイン(LeIN) CEOの芦川由香さんに話を聞いた。

“学び”での、「自分を成長させたい」思いと、「学習者に寄り沿う」大切さ
神戸大学には、文部科学省の委託を受けた実践研究の場として、全国の大学機関では珍しい授業がある。2019年からスタートした「神戸大学・学ぶ楽しみ発見プログラム」(KUPI=Kobe University Program for Inclusion)だ。これは、大学教育を知的障がいのある人に開いていく試みで、今秋、「HRオンライン」は、その授業の様子を見てきた。そして、「学ぶこと」「教えること」の大切さを実感し、「KUPI」の統括責任者であり、授業を受け持つ津田英二教授(神戸大学大学院 人間発達環境学研究科)に話を聞いた。自分を成長させたい思いと、学習者に寄り沿うことの大切さとは?

“スーパー利己的”な新入社員が、アルムナイとうまく付き合うための方法
集団生活を営んだり、企業・団体の中で働いたりするときに、自分の利益を優先する「利己的な姿勢」は軋轢や諍いを生むことが多い。そのため、「誰かのため」という利他的な姿勢が美徳とされ、仕事においては、「組織のため、会社のため」という滅私奉公のスタイルが昭和の時代は重んじられた。しかし、時代は変わり、「スーパー利己的になって、会社での自分の目的を達成してください!」と新入社員にメッセージする経営者もいる。令和のビジネス界に「アルムナイ」という言葉を広め、浸透させた鈴木仁志さん(株式会社ハッカズーク 代表取締役CEO)だ。“スーパー利己的”とは、どういうことか? 「HRオンライン」で連載執筆中の鈴木さんのオフィスを訪ね、その真意を聞いた。

たそがれ研修、役職定年……いま考えたい、50代ミドルシニアのリアルな働き方
65歳までの雇用確保措置が企業に義務化されているいま(2024年8月現在)、再雇用か勤務延長(定年退職せずに雇用される勤務)で、少なくとも65歳まで働き続ける人が増えている。そうしたなか、50代半ばで役職定年を迎え、仕事のモチベーションの低下とともに「失われていく10年(55~65歳)」に思い悩む人が多いようだ。雇用する側の企業にとっては、定年退職を控えたミドルシニア世代にどう向き合っていくかが喫緊の課題となる。これまでに、1500社以上・約13万人の人材を育成し、「コンサルタント・オブ・ザ・イヤー」(全能連マネジメント・アワード2023)を受賞した田原祐子さん(株式会社ベーシック 代表取締役/社会構想大学院大学教授)に、最新著書『55歳からのリアルな働き方』をもとに“企業とミドルシニアのこれからの在り方”を聞いた。

大学生のアクティブ・ラーニングの「学び」を、企業は生かすことができるか
学校教員はじめ、教育関係者にとっては、耳なじみのフレーズである「主体的・対話的な深い学び」――文部科学省によれば、これは、アクティブ・ラーニングから生まれる学びのあり方だが、企業経営層や人事担当者は、昨今の大学生がどのような学び(アクティブ・ラーニング)を経て社会に出ているのかをあまり把握していないのではないか。アクティブ・ラーニングのひとつであるPBLを授業科目にしている大学が増加傾向にあるが、その授業内容や目的・成果はどうなっているのか? 産学協働に長らく取り組み、“グローバルなPBL”を展開している万浪靖司さん(静岡産業大学経営学部准教授)に話を聞いた。

上司も部下も知っておきたい、“海外リモートワーク”でチームが元気になる方法
コロナ禍ですっかり一般化した“リモートワーク”だが、海外在住で日本の企業にリモートワークすることは、時差の問題などもあって、未だハードルが高いようだ。「HRオンライン」の執筆でもお馴染みの東加菜さんは、ベトナムのホーチミンに住みながら、日本の企業(michinaru株式会社)の広報担当として、フルリモートワークを続けている。“海外リモートワーク”のメリットとデメリットは何か? また、リモートワークの多い社員に人事担当者や管理職はどう接すればよいか?――HR業界に深い知見を持つ東さんならではの就労観を「HRオンライン」が聞いた。

新卒採用の成否は、学生への“フィードバック”の良し悪しで決まる!
24卒(2023年度卒業・修了予定者)の入社内定式が行われた、昨年(2023年)10月1日時点で、大学生の就職内定率は74.8%と、前年同期を0.7ポイント上回った。コロナ禍が落ち着き、労働力人口の減少に伴って、新卒採用は「売り手市場」になっている。しかし、応募学生の母集団形成がうまくいかず、良い人材になかなかめぐり逢えない企業も多い。そうしたなか、25卒採用に向けて、『志望度は面談で決まる~学生に選ばれる企業になるために~』というウェビナーが昨年(2023年)11月と12月に開催された。そのウェビナーの内容とともに、最新の“採用市場戦線”を「HRオンライン」が追いかける。
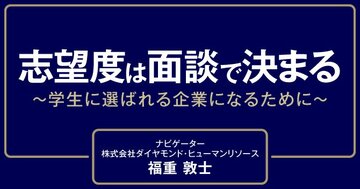
24卒生の“秋採用”で、企業が良い学生と巡り合うためのいくつかの方法
新卒採用支援を行っているダイヤモンド・ヒューマンリソース社の調査によれば、今年(2023年)のゴールデンウイーク明けの時点で、企業の内定を獲得した学生(24卒生)の比率は昨年(23卒生)を大きく上回った。しかし一方で、夏を過ぎ、秋になって、まだ内定を受けていない学生、採用枠を満たしていない企業も多くある。そうしたなか、10月から12月にかけて行われる「秋採用」は、企業にとっても、学生にとっても、お互いの活路を見出す大きなチャンスになるだろう。採用コンサルタント・採用アナリストの谷出正直さんに、企業(採用担当者)と学生(就活生)の良い出会い方を「HRオンライン」が聞いた。

年収の壁、非正規雇用、昇進拒否……“女性活躍推進”を阻む壁は何か?
ダイバーシティ&インクルージョンの礎である「女性活躍推進」――2016年4月に施行された「女性活躍推進法(女性の職業生活における活躍の推進に関する法律)」は、「働きたい女性が活躍できる労働環境の整備を企業に義務付けることで、女性が働きやすい社会を実現すること」を目的として、10年間の時限立法として施行されたものだ。しかし、年収の壁、マミートラック、アンコンシャスバイアスといった問題もあり、企業における女性の働き方は順風満帆とは言い難い。元『日経WOMAN』の編集長であり、『女性リーダーが生まれるとき』(光文社)など、多数の著書がある野村浩子さんに、企業・団体における「女性活躍推進」の現状と課題、これからの道行きを聞いた。

あらゆる人が働く職場で、それぞれ認め合い、自信と誇りを持つために
性別・年齢といった違いだけではなく、仕事の現場ではさまざまな価値観やキャリアを持つ人が働いている。いまや、企業・団体が「ダイバーシティ&インクルージョン」を目指すのは当たり前だが、スローガンが一人歩きして実現がうまくなされない組織も多いようだ。福井県鯖江市に、あらゆる人が集い、働きやすさと働きがいを感じている職場がある――株式会社メガネトップのキングスター工場。世界一の品質を生むのは、機械ではなく、そこで働く人たちの志だ。「HRオンライン」が現地を訪れ、工場長の吉田和弘さん(株式会社メガネトップ 商品開発部 部長)に話を聞いた。

「就活病」の学生のメンタルを、先輩社員や採用担当者がフォローする方法
企業・団体における、24卒生(2024年3月の学校卒業者)の採用活動が佳境を迎えている。新型コロナウイルス感染症は、「2類相当」から「5類」に移行し、就職活動を大きく変えたウィズコロナの時代も新たなステージに入った。インターンシップ改革、オンライン面接の平常化、早期化する内定出し……就職戦線が変化するなか、Z世代の就活生たちはどのようなメンタルで就活を行っているのだろう。そして、人材獲得に腐心する採用担当者は、どのように彼ら彼女らに向き合うべきだろう。書籍『内定メンタル』の著者であり、地方学生向け就活サービス「ジョーカツ」でのセミナーの講師などで全国の就活生とつながりを持つ光城悠人さんに話を聞いた。

シニア社員の“パラレルキャリア”が個人と組織にとって大切なのはなぜか?
ここ数年、「キャリア自律(Career Self-reliance)」という言葉が目立つようになった。コロナ禍や慢性的な労働力不足によって体力をなくした企業は先行きが不透明となり、雇用される側は、仕事のスキルを上げて、エンプロイアビリティ(雇用される能力)を高めなければならない。昨年2022年10月刊行の書籍『個人と組織の未来を創るパラレルキャリア ~「弱い紐帯の強み」に着目して~』の著者・中井弘晃先生(明海大学 総合教育センター/専任講師)は、「キャリア自律を促進する方法のひとつが、人との交流を伴う“学びのパラレルキャリア”の実践」だと論じる。個人と組織の双方にメリットのある「パラレルキャリア」とは何か? 中井先生が教壇に立つ明海大学(千葉県浦安市)のキャンパスで話を聞いた。

パワハラをなくすために、今日からできる、上司と部下の向き合い方
「労働施策総合推進法(通称:パワハラ防止法)」の全面施行から約1年――コロナ禍でリアル対面のコミュニケーション機会が減ったこともあり、部下の指導に腐心する上司・管理職が多くなっている。指導のひとつの手段としては「叱責」もあるが、ビジネス心理学を専門とする水口政人教授(龍谷大学・文学部)は、パワーハラスメントのない職場づくりと良好な人間関係のために、安易な叱責は不要と説く。「HRオンライン」が、龍谷大学(京都市)のキャンパスで水口先生に話を聞いた。

介護業界で、誰もが気持ちよく、長く働き続けるために必要なこと
高齢化が進む日本において、介護業界の人手不足が深刻な問題になっている。離職率の高さに加え、新型コロナウイルス感染症の影響で、働きたくても働けない求職者も多いようだ。職場環境、賃金、人材育成……業界や介護施設が抱える課題に向き合いながら、いま、介護業界で働く人たちをどう増やしていけばよいのか。「介護未経験・資格なし」の人材の就労と定着を進める、派遣業界大手のスタッフサービスグループ/スタッフサービス・メディカルの平井真さん(株式会社スタッフサービス・ホールディングス 執行役員)に話を聞いた。
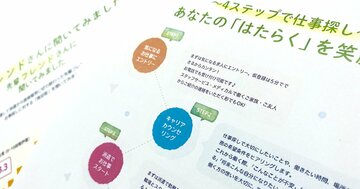
JTの内定者懇親会が教えてくれる、内定者同士の“つながり”の大切さ
あと2カ月ほどで“23卒生”が社会に飛び立つ。その23卒生の採用活動において、「内定者フォローや辞退防止のために実施したこと」を企業に聞いたところ、従業員501名以上の大規模企業も500名以下の中小規模企業も、回答の1位が「内定者懇親会」だった。コロナ禍で、内定者向けのイベントや内定式が対面では行いづらくなっている昨今、「内定者懇親会」はどのような内容で、どう開催されているのか――内定者同士に加え、人事担当者と内定者の関係を構築することで参加学生の入社意欲を高めている日本たばこ産業株式会社の三島紀子さん(日本マーケットCountry P&C Recruitment)に話を聞いた。