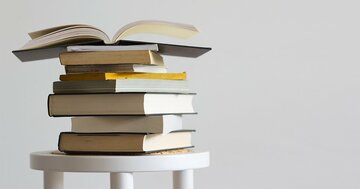たとえば、普段は手に取らないようなジャンルの本がレコメンドされたとき、彼らはそれを新しい発見の機会と捉えます。
自分の知見を広げるきっかけになるかもしれない、と考えて、あえてその本を読んでみる。すると、思いがけない学びや気づきが得られることがあるのだとか。
また、レコメンドを通じて出合った本が、人生を大きく変えた経験を持つ人もいるそうです。ある5%社員は、Amazonから勧められた1冊のビジネス書が、自身のキャリアの転機になったと語ってくれました。その本に出合わなければ、今の自分はなかったかもしれない。そう振り返る彼の言葉が、強く印象に残りました。
Amazonのレコメンドは
あくまでも読書の入り口
しかし、ここで注目すべきは、5%社員が、レコメンドにすべてを委ねているわけではないということ。彼らの多くは、レコメンド機能を参考にしつつも、最終的には自分の判断を重視しているのです。
レコメンド機能にも限界はあります。
Amazonの優れたアルゴリズムも、あくまで過去のデータに基づくもの。未知の分野の本や、自分の視野を大きく広げてくれるような本は、レコメンドされにくいのが現状です。
だからこそ、彼らはレコメンドを鵜呑みにするのではなく、批判的に吟味する姿勢を持っているのだそうです。レコメンドされた本も、書評や要約を読み、友人や同僚の意見を聞き、書店で実際に手に取ってみる。そうすることで、本当に自分に合った本を見極められると考えているのです。
Amazonのレコメンドは、あくまでも読書の入り口に過ぎません。そこから先は、自分の好奇心と判断力を頼りに、新しい知識の世界を探求していくのです。
5%社員は、レコメンドとスマートに付き合っています。時にはレコメンドに耳を傾け、時には自分の直感を信じる。そんな柔軟な姿勢が、彼らを卓越した読書家へと導いているのかもしれません。
完璧を求めるよりも
吸収率70%を目指そう
5%社員は完璧を目指して読書をしません。完璧を目指してしまうとストレスが増大し、読書そのものが負担になってしまうからだそうです。
彼らは読書を自己成長や知識の獲得のための道具として利用していますが、同時に楽しむことも忘れません。読書を1つの楽しみとして、あるいはリラクゼーションの時間として捉えているのです。