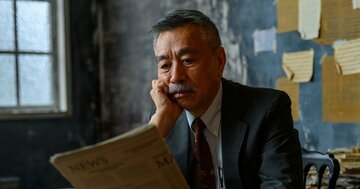定年前からできる、認知症リスクを下げる“人間関係”の築き方
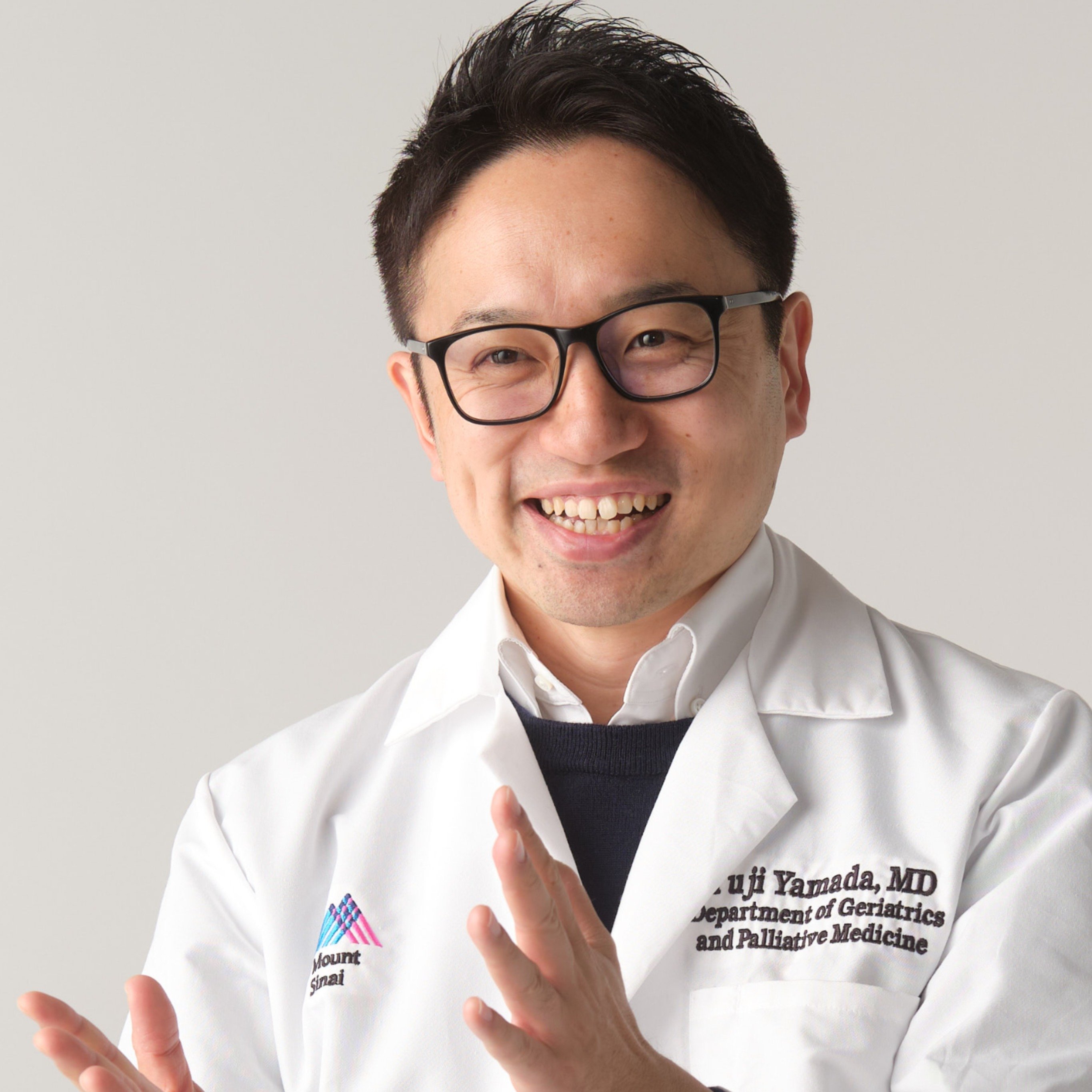 山田悠史
山田悠史マウントサイナイ医科大学(米ニューヨーク)老年医学・緩和医療科医師。米国老年医学・内科専門医、医学博士。慶應義塾大学医学部を卒業後、日本全国各地の病院の総合診療科で勤務した後、2015年に渡米。現在は高齢者医療を専門に診療や研究に従事している。国内ではWEBマガジン『ミモレ』、ニュースメディア『NewsPicks』などで医療・健康情報を発信するほか、AIと医療をつなぐ合同会社ishifyの共同代表を務める。米国では、NPO法人FLATの代表理事として在米日本人の健康を支援する活動にも力を入れている。 著書に、『最高の老後 「死ぬまで元気」を実現する5つのM』、『認知症になる人 ならない人 全米トップ病院の医師が教える真実』(共に講談社)など。
人間関係と孤独感をそれぞれ個別に分析した研究によると、孤独感そのものでは認知症リスクの増加は確認されなかった一方で、社会的なつながりやサポートを欠いている人では、認知症のリスクが高まるという報告があります。
さらに、社会的に孤立していると、ストレスへの耐性が弱まるだけでなく、セルフケア――たとえば、病院に行くとか、生活を整えるとか、そういったことが疎かになりやすい、ということも知られています。
その結果、健康を害しやすくなり、病気の発見も遅れてしまう。そうした健康の悪化が、結果的に認知症のリスクを高めてしまうことがあるんです。
――お話を伺っていると、定年前から積極的に人間関係を維持する努力が必要になってきそうですね。仕事を通じて人間関係を築いてきた方は、退職後、それらのつながりをどう維持し、広げていけばよいのでしょうか?
定年後の時間をどう過ごしたいかによって、築くべき人間関係のあり方も変わってきます。まずはご自身が何に没頭したいのか、どんなことをしていきたいのかを伺ったうえで、私は提案をするようにしています。
たとえば、会社を辞めた後でも、地域で参加できるボランティア活動などは数多くあります。「友達を作らなければ」と肩に力を入れなくても、何かしらの活動を通じて、自然と仲間が増えていくケースも少なくありません。