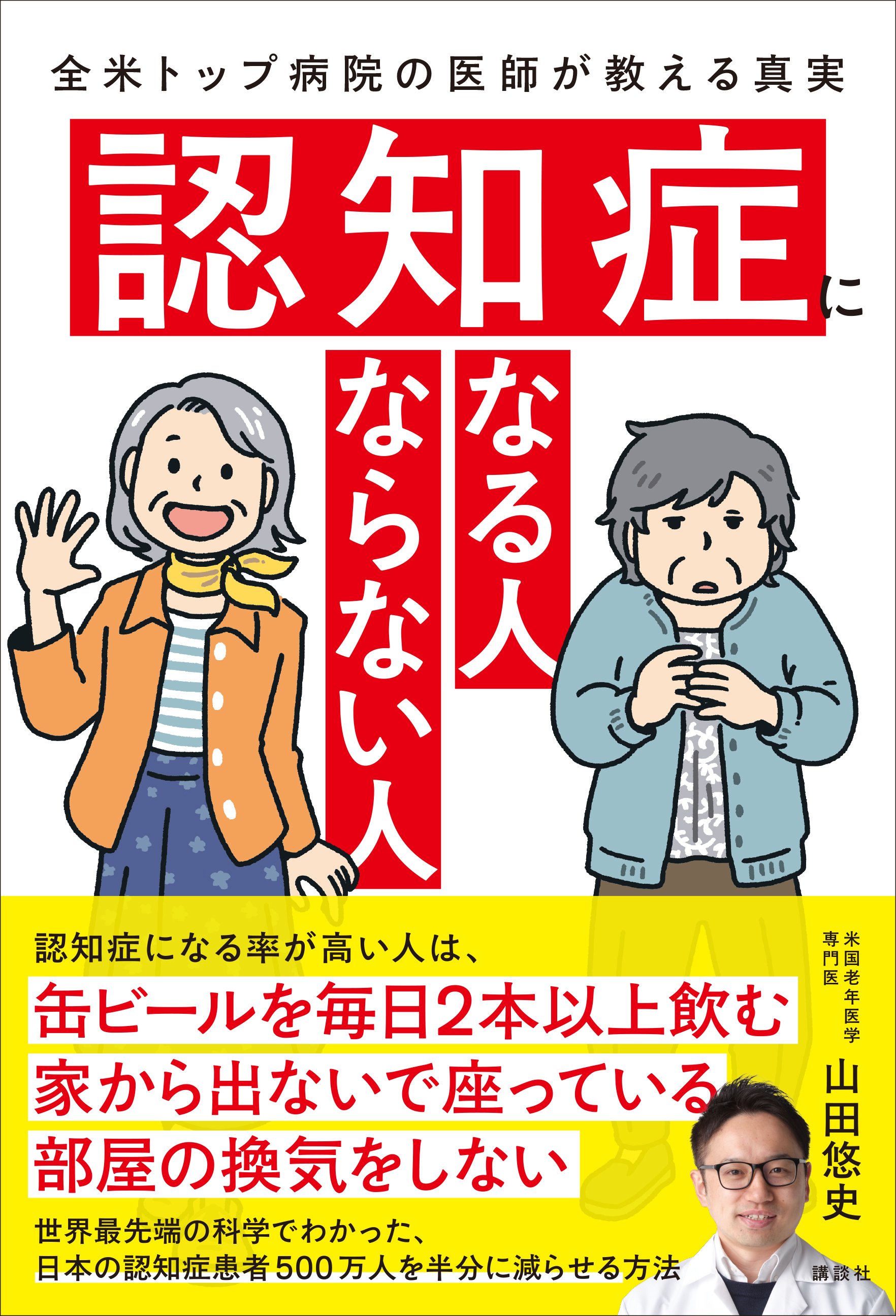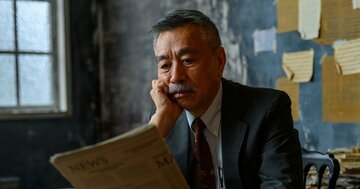「年に1回の眼科検診」がおすすめのワケ
なかでもお酒については、なかなか難しいテーマではありますが、やはり時間に余裕ができると、飲酒量が増えてしまうというのはよくあることです。だからこそ、先ほど申し上げた「運動」と同じように、定年後の空いた時間をどう使うかを意識しておくことが大切です。
たとえば、以前からやってみたかった趣味に取り組んでみるなど、時間の使い方を見直すことで、結果的にお酒を飲む量が自然と減っていくケースもあります。
もうひとつ大事なのが、年齢と飲酒の関係です。若い頃は平気だったお酒の量、たとえばビール2杯でも、30代の頃は何ともなかったかもしれません。しかし、60代になると肝臓の代謝機能が少しずつ落ちてきます。同じ2杯でも、体への負担は大きく変わってくるのです。
その結果、転倒して骨折してしまったり、心臓に負担がかかったり、あるいは睡眠の質が落ちてしまうなど、健康への影響がさまざまなかたちで現れるリスクが高まります。
「昔と同じ量を飲んでいるだけなのに、なんだか調子が悪い」――そんな声を聞くこともありますが、その“同じ量”が、年齢を重ねた今では“同じではなくなっている”ということに、ぜひ気づいていただきたいですね。
――50代以降から予防を始める場合は、どのようなことを意識したらよいでしょうか?
まずは「年に1回の眼科検診」がおすすめです。目と耳の機能を保つことは、脳への情報の「入口」を守るうえで非常に大切だということが知られています。外出時にサングラスを使って、紫外線から目を守ることも白内障や加齢黄斑変性という病気などの予防になります。
あとは、頭への衝撃を含め、頭のけがを経験した人は、認知症リスクが約66%から84%程度の割合で高まることが知られているので、自転車に乗るときなどには、ぜひヘルメットを着用してください。
――バイクはともかく、自転車に乗るときにヘルメットをかぶる習慣がない人は多そうですね。サングラスも日本人には少しなじみが薄いかもしれませんが、心がけたいですね。
その他、一般健康診断やワクチン接種、睡眠のリズムを整えることも重要です。例えば、帯状疱疹の発症を予防するワクチンには、認知症予防効果がある可能性が繰り返し示唆されているので、50歳以上の方はぜひ接種してください。
また、高齢になり配偶者に先立たれた方や、家事経験が少ない男性が急激に生活能力を落とし、老け込んでしまうというケースは珍しくありません。今からでも家事に取り組んでみるのも、良い認知症予防になるのではないでしょうか。