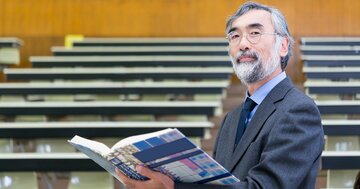しかも、各研究領域や地域においては、有力大学の強弱に違いがあるから、特定の地域の特定の領域に関わる大学教員市場は、東京大学や京都大学をはじめとする一部有力大学出身者の寡占状態になりかねない。
そして、そのような一部大学出身者の大きな存在は、大学教員の人間関係の中に、学生時代からの先輩・後輩関係として反映され、ひいては年功序列的な関係となって表れる。「あいつは学生のときからあんな奴だった」。そんなことを還暦間際まで言われつづけるのは、この業界だけかもしれない。
そして、それは当然のことながら、大学教員の人間関係における矛盾となって表れる。
建前は能力主義だが……
若手を苦しめる年功序列
大学教員の世界では――少なくとも従来は――年齢は人事を考える上で重要な基準であったし、また、若い人を年長者よりも上の職階に付けることを忌避することが多かった。
とりわけ、同じ出身大学、同じ研究室出身の研究者の間で、年齢と職階の上下を入れ替えるのは、多くの場合において禁忌であった。
しかし、そのことはときに「良い研究/仕事をすれば報われる」そう教えられ、信じて切磋琢磨してきた人を、落胆させる。
大学教員の世界では、いったんテニュア(編集部注/大学教員に与えられる終身在職権のこと)を獲得してしまえば、問題を起こして懲戒されることはあっても、職階を下げられることはほぼないので、研究業績等で大きな成果を上げていない人が、より優秀な若手より上位の職階に居座りつづけていることも珍しくない。
能力主義の「建前」と年功序列の「現実」は、結果として、大学教員の間で、同じ大学を卒業した似た年齢で、似た研究をしている人たちの間に、きわめて狭いライバル関係を作り出す。
彼らは同じ論文発表の機会や同じ研究資金、そして同じ大学の同じ職階のポストを争うことになるからだ。さらにいえば学閥が羽振りを利かせているかぎり、自らの成功のためには所属する学閥の中での序列も重要になる。