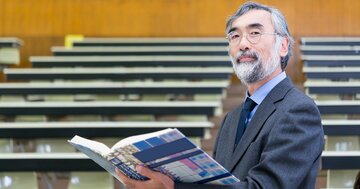自分は努力したと思い込み
他人を怠け者と決めつける
加えて、教員には自らの立場を錯覚しやすい環境がもう1つ存在する。多くの大学教員は、大学院生時代から研究を続け、その成果に一定の評価を得たことで、その職を獲得している。
だから彼らは、自らの成功は自らの努力と才能の結果であり、結果が出ない人は努力と才能が足りないからだ、と考えがちになる。典型的な「生存者バイアス」というやつだ。
現実には、研究面での成功も多分に環境や偶然に左右されるものであり、当人の努力や才能によってのみ得られたものではないのだが、これに気づかないままでいると、さまざまな仕事で成果を出せない人たちを、怠惰で無能な人呼ばわりする大学教員が続出することになる。
こうして大学教員が事務職員や学生、さらには自らより若い教員に対して、心無い言葉を投げかけ、傷つけるシーンが頻発する。
これらは大学教員が学生や事務職員に対して、自らが一定の「権力」を有していること、そしてその行使により、他人を容易に傷つけ得ることに無自覚であることに由来している。深く注意しなければならない、点である。
だからこそ、このようなハラスメントの処理も、各部局長の重要な仕事の一部になる。現在の大学では、多くの場合ハラスメントを担当する委員会が設けられ、その処理に当たっているが、その委員会に誰を配置するかを決めるのは、筆者のような部局長の仕事の1つになる。
多くのハラスメントは、先に述べたように、教員等が有している「権力」と密接に関係しているので、被害者をその「権力」から守り、少しでも声を上げやすい環境を作るのも、重要である。
また、ハラスメントにかかわる問題は、単に被害者を守り、加害者を処罰すれば済むわけではない。ハラスメントの被害者である学生や教職員は、その後も大学における研究や仕事を続けることが多いから、彼らをとりまく人間関係をいかに修復し、復帰しやすい環境を作るかもきわめて大事である。
破壊された人間関係が修復されず、殺伐とした人間関係だけが残されれば、学習や仕事の効率は上がらない。それでは部局のパフォーマンスは下がるばかりだ。