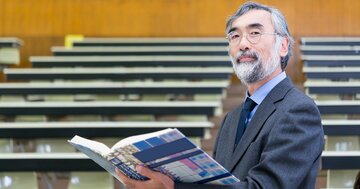だからときに、大学教員は自らと異なる領域の研究をし、異なる大学を卒業し、異なる地域の異なる大学で仕事をしている人とのほうが、同じ「学閥」や研究室出身の人々とよりはるかに仲が良かったりする。
それは縄張り意識を持つ鮎が、他の鮎とは共存できなくても、他の魚とは共存できるのと似ているかもしれない。よほど大きな大学でないかぎり、1つの分野の専門家は1人で十分であり、その縄張りを失えば生きてはいけないからである。
先生と呼ばれ続けた結果
勘違いモンスターが生まれる
大学教員に関わる問題の1つに、ハラスメントを巡る問題がある。ハラスメントには、学生と教員の間のもの以外に、教員同士の間のものや、教員と事務職員の間のものもある。
大学の現場でハラスメントに関わる問題が絶えないのは事実であり、この状況は改善されなければならないし、そのためのさまざまな措置も取られている。にもかかわらず教員によるハラスメントが絶えない背景には、構造的問題がある、と筆者は考えている。
大学教員は就職すると「先生」と呼ばれ、大学の内外で丁重に扱われる。しかし、このような状況はときに、教員をして自らが突如として「偉い人」になったかのように錯覚させる。
大学の組織では、さまざまな決定権を持っているのは、事務方の職員よりも教員側であり、そのことも教員が自らの立場を勘違いする理由になる。
同じことは、学生との関係についても言うことができる。多くの大学にて教員は自らの担当する授業の成績評価において、絶対的な権限を有している。だからこそ、学生は教員の意向に逆らうことは難しいし、さまざまな思いを抱えていても、これを表面に出さずに抑えている。
しかし、教員の中にはこの状況を、学生が自らの意に賛同しているものだと錯覚し、自らの意志を学生に押し付けていることに気づかない人が出る。
ハラスメントの1つである、セクシャルハラスメント、つまりはセクハラにも、こうした教員側の「思い違い」が介在していることが多い。