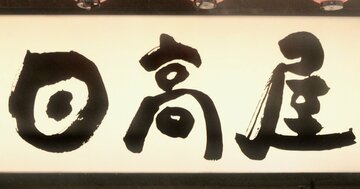Photo by Shogo Murakami 衣装協力=イザイア/ISAIA Napoli 東京ミッドタウン メイク協力=ラ・メール スタイリスト=川田真梨子 ヘアメイク=林摩規子
Photo by Shogo Murakami 衣装協力=イザイア/ISAIA Napoli 東京ミッドタウン メイク協力=ラ・メール スタイリスト=川田真梨子 ヘアメイク=林摩規子
火付盗賊改方の長官を2度も務めた
超人・長谷川平蔵の人間観
――企業における後継者育成も、多くの経営者が直面する重要な課題です。ご長男である市川染五郎さんも同じ俳優の道を歩まれていますが、次世代を担う人材に「事業の本質」を継承していく上で、どのような機会や経験が最も重要だとお考えですか。
幸四郎:私が何かを教えるというよりは、彼自身が現場で何かを感じ取ってくれればよいと思っています。テレビスペシャル「鬼平犯科帳 本所・桜屋敷」で息子は、私が演じる長谷川平蔵の若い頃、銕三郎を演じましたが、そのこと自体に何か特別な感慨があるというわけではありません。
それよりも、彼が俳優として、京都の松竹撮影所という、時代劇のプロフェッショナルたちが集う現場に再び立てたこと。そのチャンスをいただけたことが、何よりうれしかったのです。
この世界には、マニュアル化できない知恵や技術があふれています。それを肌で感じ、自分のものにしていく経験こそが、彼を俳優として成長させてくれるはずです。親が答えを与えるのではなく、彼自身が現場で学び、自分の力でつかみ取る機会を尊重したいと思っています。
――最後に、人間の複雑さというテーマに立ち返ります。「鬼平犯科帳」にはさまざまな名ゼリフが登場します。「鬼平犯科帳」の最新第6弾「暗剣白梅香」では、「人間とは面妖なものよ」(「面妖」とは、不思議で不可解な様子のこと)というセリフも印象的でした。
幸四郎:少し漠然とはしていますが、この言葉は作品の核を突いています。火付盗賊改方という仕事は、凶悪犯を取り締まる過酷なものでしたが、長谷川平蔵は火付盗賊改方の長官を2度も務めた超人的な人物です。平蔵の口からこの言葉が自然と出てくるのは、人間に対する深い洞察と、強靭(きょうじん)さがあるからでしょう。
―――
「クセのある部下」という言葉自体が、すでに相手にレッテルを貼る行為なのかもしれない。松本幸四郎が語る長谷川平蔵の組織術は、相手の経歴や性格を「クセ」としてではなく、一人の人間の「個性」として丸ごと受け止めることから始まる。リーダー自身が完璧ではないことを認め、多様性を受け入れる懐の深さを持つ。それは、どんなマネジメント理論よりも深く、人の心に響くものだった。