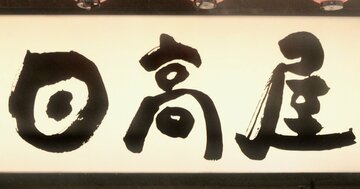Photo by Shogo Murakami 衣装協力=イザイア/ISAIA Napoli 東京ミッドタウン メイク協力=ラ・メール スタイリスト=川田真梨子 ヘアメイク=林摩規子
Photo by Shogo Murakami 衣装協力=イザイア/ISAIA Napoli 東京ミッドタウン メイク協力=ラ・メール スタイリスト=川田真梨子 ヘアメイク=林摩規子
経歴も価値観も異なる、いわゆる「クセのある部下」たち。彼らの能力をいかに引き出し、チームの力に変えるか。これは、現代のリーダーが直面するダイバーシティーマネジメントの核心的な課題である。「鬼平犯科帳」で松本幸四郎演じる長谷川平蔵が率いるチームは、まさにそのモデルケースだ。元盗賊の密偵から与力・同心まで、多種多様な人材が彼のもとで躍動する。松本幸四郎が語る平蔵の組織術は、驚くほどシンプルだった。(歌舞伎俳優 松本幸四郎、取材・構成/小倉健一)
「何を言ってもダメだ」と
決めつけない
――組織のリーダーは、多様な個性を持つメンバーをまとめ、一つの目標に向かわせるという重要な役割を担います。「鬼平犯科帳」の長谷川平蔵が率いるチームには、与力・同心だけでなく、元盗賊などの密偵も含まれる、非常に多様な人々がいます。ビジネスの現場では、経歴や価値観が異なる「クセのある部下」のマネジメントに悩むリーダーも多いのですが、平蔵はなぜ、彼らを一つのチームとして機能させることができるのでしょうか。
松本幸四郎さん(以下、幸四郎):まさに、そこが平蔵のリーダーシップの重要なところです。平蔵は、相手が盗賊であっても「悪人」というレッテルを貼りません。あくまで「人」として見ている。
「善人」や「悪人」といったレッテルを貼らず、一人の人間として向き合っています。「悪人だから何を言っても、何をやってもダメだ」と決めつけず、その人の背景や人生そのものを見て、良い部分があるならともに仕事をする。
――「人として見る」。言葉にするのは簡単ですが、実践するのは非常に難しいことだと思います。過去の失敗や経歴にとらわれず、相手を信頼するというのは、大きなリスクも伴います。
幸四郎:平蔵自身も、若い頃は無頼の限りを尽くしています。その過去を隠すことなく、すべてをさらけ出した上で「長官」として立っている。その懐の深さ、人間としての器の大きさが、多様なバックグラウンドを持つ者たちを惹(ひ)きつけ、一つの強いチームを作り上げているのだと思います。
悪いことをした人間でも、その中にまだ救いがあるのではないかと見抜く力。それを持っているのが平蔵です。
人間性まで否定しないから
相手も心を開く
――なるほど。リーダー自身が完璧ではなく、自らの弱さや過去をさらけ出しているからこそ、多様な人材を受け入れる土壌が生まれるのですね。
幸四郎:そうですね。悪は悪として断固として裁くけれど、悪いことをしたからといって、その人間性まで全否定するわけではありません。あくまで一人の人間として向き合うからこそ、相手も心を開く。言葉だけのやり取りではない、もっと深いところでのつながりが生まれるのではないかと思います。
彼が裁いているのは犯した「罪」であって、その人の「人間性」そのものではない。その区別が明確だからこそ、人は彼を信頼し、過ちを犯した者でも更生の道を歩むことができるのだと思います。
それが、のちのち平蔵が創設する「人足寄場(にんそくよせば)」(無宿者や犯罪者の更生施設)の理念にもつながっていくのでしょう。