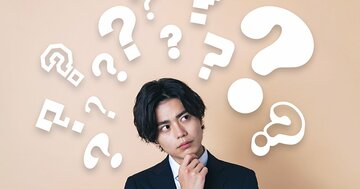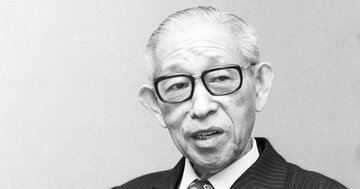よく「部下とは距離を置くべきでは?」という考え方をする人もいるが、「距離」を重視するなら、チームが成果を上げるために最適な「距離」の定義をもっと明確にすべきだ。少なくとも、部下に「共感」も「共鳴」もせず、一方的に数字やルールを押し付けた組織がどのような結末になるかは想像できるのではないだろうか。
ルールや仕組みだけがあっても、それを自発的に回してくれるメンバーがいなければ成果は上がらない。
カリスマ性を凌ぐ「共感マネジメント」
「自分にはカリスマ性や人徳がない」と自覚しているリーダーは、むしろ共感力で勝負すればいい。部下の悩みや不安に耳を傾け、「そういう気持ちがあるんだね」と受け止めるだけでいい。騙されたと思って一度試してみれば、すぐにその効果がわかるだろう。
これは、1on1の時間を確保したり、週1回の全体ミーティングで5~10分ほど部下の感情を引き出すコーナーを設けたりすることで仕組み化できる。わざわざ大演説をする必要はない。本音が受け入れられる組織では、「自分がここで走る理由」をメンバー自身が自然に見つけ出そうとするからだ。鼓舞するのではなく、「共感」しよう。
「共感」の仕組み化
「共感」と「共鳴」を意識して日頃のコミュニケーションをとるだけで、部下との信頼関係の構築や合意形成はしやすくなる。
ただ、「仕組み」として具体的に取り入れたいのであれば、マネジメント初期に部下の「仕事への価値観」をヒアリングすることをおすすめする。形式は、1on1で30分から1時間程度が望ましい。効果的にヒアリングをするためにおさえるべきポイントは次の3つだ。
(1)最初に自己開示する
(2)「沈黙」の時間をつくる
(3)部下に「共感」か「共鳴」をする
それではポイントごとにみていこう。
(1)最初に自己開示する
部下へのヒアリングを目的にすると、ついあらかじめ決めておいた質問を次々投げかけたくなるかもしれないが、それでは警戒心が邪魔をして部下が自己開示をしてくれない。あるいは、どのようなことを聞きたいのかがわからず、「仕事のモチベーションですか?一応ありますけど」程度の気のない答えしか返ってこない。