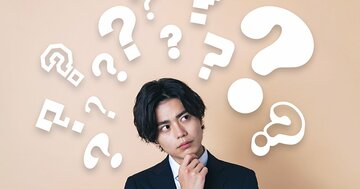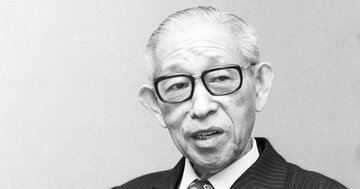写真はイメージです Photo:PIXTA
写真はイメージです Photo:PIXTA
「今の管理職は忙しすぎる」経営コンサルタントをしていると、こうした声をよく聞く。実際、働き方改革やハラスメント防止法など、新しいビジネストレンドが管理職の負担を増やしていることは確かだ。だが、そんな状況でも定時に仕事を終えて成果を出すリーダーはいる。忙しすぎて残業続きのリーダーと何が違うのだろうか?
「いまの管理職は忙しすぎる」
経営コンサルタントの仕事をしていると、このような現場の声をよく耳にする。たしかに、ここ10年ほどで急速に普及した働き方改革やテレワーク、ハラスメント防止法などの新しいトレンドの多くが、管理職の負担を増やしていることは事実だ。
ただし、そんな現代においても、涼しい顔で定時内に仕事を終え、高付加価値を生み出し続けるリーダーはいる。
定時帰りで成果を出すリーダー
忙しすぎて成果を出せないリーダー
両者の違いはどこにあるのだろうか。それは、言葉の多さだ。
成果を出すリーダーの多くは、朝礼後、いくつかのミーティングを除けば、部下との会話はほぼゼロだ。日中、リーダーは黙々と自分の仕事を片づけていく。部下はわからないことがあれば、マニュアルを見たり、同僚に相談したりして、リーダーの手を止めたりはしない。
一方、成果を出せないリーダーの多くは、口頭指示や質問などの対応に追われ、自分の仕事は定時後や休日に片づけることになる。あるいは、「やらなくてはいけない」と思いながらも、「やらない」選択をとる仕事が増えていく。
ここまで聞いて、「そうか。それなら明日から一言も話さないようにしよう」と結論を急ぐのはやめてほしい。言葉の多さは、一つの指標にすぎないのだ。言葉がなくても成果が上がる仕組みがあるかどうかの指標である。
もし、リーダーが言葉を尽くさないと成果が上がらないのだとしたら、それはチームに仕組みがない証拠だ。あなたのチームはどうだろうか?あなたがいないと動けない部下はどれくらいいるだろうか?
リーダーが言葉の力に頼っている限り、チームは機能しない。私が現場で見てきた限り、場当たり的な口頭指示や部下を鼓舞するための激励は、仕組みがないチームがいますぐ崩壊しないための応急処置にすぎないからだ。
リーダーは、マイナスをゼロにする仕事にばかり時間をとられ、成果を上げるための戦略的な仕事に着手できない。忙しいのに成果が上がらないという苦しいチーム運営を続けていれば、リーダーの心身はすぐに限界を迎えてしまうだろう。
せっかくプレイヤーとして優秀だったあなたが、そんなところでキャリアに躓(つまづ)いてしまうのはやり切れない。いまが苦しいリーダーこそ、勇気を持って、仕組みづくりに時間を投じてほしいのである。