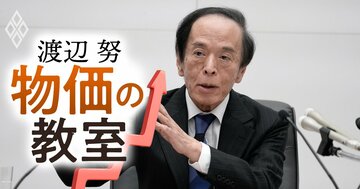Photo:JIJI
Photo:JIJI
財政拡張予想し国債利回り上昇
異次元緩和の“後遺症”が残る困難
上昇基調が続く超長期債の利回りは、参議院選挙後の財政拡張への思惑もあって、7月第4週も新発20年債や30年債、40年債で強含み、新発30年債は23日、前日比0.040%高い3.062%で取引を終えた。長期金利の指標である10年国債利回りも、一時、1.6%を超え(引け値は1.590%)、2008年10月以来の約17年ぶりの高水準だ。
参院選では、与野党がともに財政拡大を伴う経済対策の実施を掲げたが、より財政拡張的な政策を掲げる野党が議席を伸ばした。23日に日米関税交渉の合意が発表され、日本銀行の利上げを巡る状況が改善されたという見方も長期金利上昇の要因となっている。長期的な財政規律に対する市場の懸念がここへ来て一層強まったわけではないが、今後の財政拡張に対する懸念の根強さが確認された形だ。
日銀は、6月の金融政策決定会合で、長期国債買い入れ減額計画を見直し、2026年第2四半期からは現行の毎四半期4000億円ずつの減額から同2000億円ずつと、ペースダウンをするものの、買い入れ減額を続けることを決めたが、難しいかじ取りが予想される。
植田和男総裁は、6月決定会合後の会見で、長期金利は金融市場で形成されることが基本との考えを強調、「国債買い入れ額をさらに減額していくことが望ましい」と、金融政策の正常化という基本方針を維持する下で、市場機能の回復を進める姿勢を強調した。
同時に、「減額ペースが速すぎると市場の安定に不測の影響を及ぼす可能性もある。両方のバランスを勘案した」と、国債市場の安定に配慮するための柔軟性を確保しながら、予見可能かつ段階的な形で買い入れ減額を進める考えを語った。
しかし、国債買い入れ減額を巡っては、国債市場の安定のほかにも、異次元緩和で購入した巨額の保有国債への対応や国債安定消化への配慮など、多くの課題が浮き彫りになっている。