
井上哲也
FRBは1月FOMCで物価と雇用のリスクの低下を理由に政策金利据え置きを決め、3会合続けてきた利下げを停止した。ファンダメンタルズの面からは追加利下げの必要性が低下したが、トランプ大統領は次期議長にウォーシュ元FRB理事を指名、利下げ圧力を強める。米経済の安定維持、FRBへの政治圧力の防波堤として金融市場の「警鐘」がますます重要になる。

日本銀行の追加利上げは、高賃上げや設備投資増など内需の堅調に加え、円安による物価上昇回避で高市政権とのあつれきが生まれなかったなどの好環境が追い風になった。ただし、2026年以降の「緩やかな利上げの継続」には、日銀の言う基調的物価上昇率や中立金利について市場などに説得力のある説明をする必要がある。

FRB(米連邦準備制度理事会)が3会合連続の利下げを決め、パウエル議長が政策金利は中立金利の推計レンジ内との考えを示したことから、「利下げいったん停止」の見方も市場では強まる。だがFOMC(米連邦公開市場委員会)メンバーでは政策金利の見通しにばらつきがあり、来年はパウエル議長の後任人事が予定されるなど、利下げ打ち止めかどうかはなお不透明要因が残る。
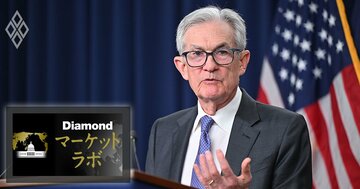
日銀が追加利上げを見送ったことには、積極財政・緩和維持を掲げる高市早苗新政権への配慮やトランプ関税の日米経済への影響の見極める必要など、いくつかの理由が“混在“すると考えられるが、最大の要因は、来年春闘などによる賃上げ上昇率が物価上昇率を上回り実質賃金がプラスになることに、まだ自信が持てないことがあるようだ。

9月FOMC(米連邦公開市場委員会)で6会合ぶりの利下げ再開を決めたFRB(米連邦準備制度理事会)のロジックは、米経済が堅調としながら雇用悪化のリスクがあるという分かりにくいものだ。利下げ圧力を強めるトランプ政権への忖度(そんたく)を疑わせる余地があり、利下げの一定の継続で経済成長を下支えするなどのシンプルな利下げロジックに変える必要がある。
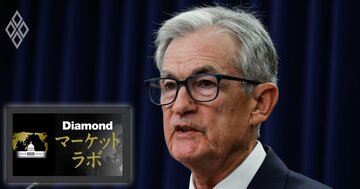
日本銀行が7月の金融政策決定会合で4会合連続の政策金利据え置きを決め、為替市場では円安が進んだ。だが、金融市場が追加利上げに対して過度に否定的な見方を持つことには副作用も多い。日銀は、緩やかな利上げの継続という基本方針を維持するために、利上げのロジックを改めて検討し、それを明確に伝える必要がある。

日本銀行は金融政策正常化で2026年4月以降も国債買い入れ減額を続けることを決めたが、超長期債の利回り上昇が10年国債金利にも波及する兆しもみられる。巨額保有国債のストック効果の金融政策への影響や国債安定消化への配慮も求められ、国債減額を円滑に進めるには多くの課題が残る。

FRBはトランプ関税によるインフレ圧力の高まりは一時的なものとみて、インフレ収束後に年内2回の利下げで景気を下支えするシナリオを描くが、関税引き上げ分の価格転嫁やトランプ減税の消費などへの影響が出る時期は不確かだ。移民流入規制による労働供給の減少でインフレ圧力が長く残る可能性もあり、シナリオ通りになるかは不透明だ。

日本銀行はトランプ関税などの影響を挙げ5月展望レポートの経済・物価見通しを下方修正し、物価上昇基調が2%目標に達する時期も実質的に1年先送りした。だが企業の賃上げや価格転嫁などの積極化や日銀の先を見越した政策運営を考えると、日銀の次回の利上げが単純に1年先送りされるとは限らない。

3月FOMC(米連邦公開市場委員会)はトランプ政策の影響の見極めから政策金利据え置きを決めたが、新たな見通しでは2025年のインフレ率を上方修正したものの関税引き上げの影響は一時的で、景気への下押し圧力もそれほど強くないとの予想から年内2回の利下げ見通しは維持された。だが家計や企業のマインド次第でシナリオが崩れる懸念も残る。
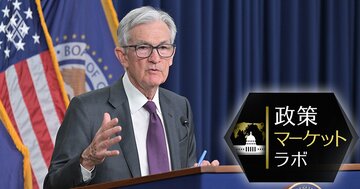
日本銀行は1月金融政策決定会合で3回目の利上げを決め金融政策正常化をさらに進めたが、会合に向けては市場で当面は政策金利を据え置くとの予想もあり、市場との認識の共有は十分とはいえなかった。年内、さらに利上げが見込まれるが、インフレ期待上振れリスクへの対応や国債買い入れの運営方針の明確化などの課題も残る。

日本銀行が公表した非伝統的金融政策についての「多角的レビュー」は、インフレ期待への効果は下回ったが、 全体としては日本経済にプラス効果が上回ったと総括した。しかし国債大量買い入れに伴う副作用が今後も大きいなど、将来、非伝統的金融政策を行う場合の課題をむしろ示唆する内容となっている。

日本銀行は10月金融政策決定会合でも9月会合に続き追加利上げを見送った。だがその一方で米国経済の減速動向を見極めるとして、追加利上げの判断には「時間的余裕がある」としてきた姿勢を修正した。7月のサプライズ利上げでの市場の混乱以前の金利正常化の基本シナリオに“回帰”したと考えられる。
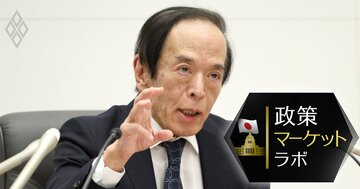
米連邦準備制度理事会(FRB)は9月FOMCで政策金利を0.50%引き下げる4年半ぶりの利下げを決めた。失業率上昇などの雇用情勢の軟化から下げ幅を通常の2倍に拡大したが、今後の利下げペースは不透明だ。インフレ再燃の懸念や米国経済の中立金利の水準が実質的に上昇している可能性があるからだ。

日本銀行は国債買い入れ減額と同時に政策金利の追加引き上げを決めた。個人消費に弱さが見られる中で、金利上昇につながる国債買い入れ減額との「同時利上げ」の予想は少なかったが、賃上げ波及など景気と物価の好循環に自信を深めていることや円安対応を意識したことが考えられる。

日銀は14日の金融政策決定会合で国債買い入れ額を現在の「月6兆円程度」から減らしていく方針を決めた。7月に具体的な減額計画を決めて実施する。3月の利上げに続き、国債買い入れによる量的引き締め策も開始することになるが、異例の“事前予告”には国債や為替市場の不安定化を避けたい思惑が感じられる。

日銀は「YCC柔軟化」を皮切りに短期金利の調節による伝統的政策へ回帰を目指しているが、巨額政府債務などのため国債の安定消化の重要性は変わりそうになく、長期金利の影響を行使する枠組みから完全に決別するのは難しそうだ。

日銀がYCCの運用「柔軟化」を決めたのは実体経済の好転などによる物価の上振れリスクを重視し金利上昇に備えたものだ。金融緩和の持続性を高めるというのが日銀の表向きの狙いだが、大規模緩和の終わりの始まりと考えたほうがいい。

直近の国際金融都市ランキングで、東京が21位とトップ20からも外れたのは調査会社や評価の仕方に疑わしい点がある。だが、重要なのは目指す国際金融都市のビジョンを固め、足りない点を改善することだ。

物価上昇が続き「緩和維持」の植田日銀への世論の風当たりは“ハネムーン期間”が過ぎ変わる兆しだ。7月の展望レポートでは物価見通しが上方修正される可能性が高いが、植田総裁のコミュニケーション力が問われる局面だ。
