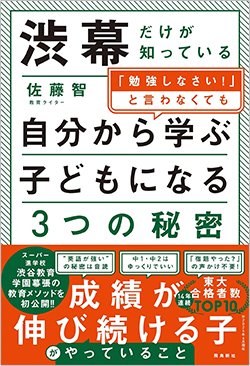・学習を怠けてついていけなくなってしまっても自己責任・進学の選択肢が多様であること
・マラソン大会前日に友達と大量の「雨フレフレ坊主」を作って吊るした。担任から呆れられた
・生徒が「やりたい」といったことは、筋が通っていてスケジュールが許せば、できる限り実行させてくれた
・部活動でそれまで行われてなかった合宿を「やりたい」といったときに、企画書を渡して説明したら承認してくださった。でも、合宿にかかる10万円程度の金銭を1人で払いに行ったときは「自由には責任が伴うとはこういうことか」と思った(大金なので顧問が引率、ないし支払いに行くべきでは?と少し思った)
・高校3年生のとき、文化祭で出し物を出すか出さないかもクラスごとに任せてもらっていた。「勉強に集中したいクラスは出し物はしない」といったことも自由。他の高校でも、そういった選択肢があるものだと思っていたけれど、卒業してそれが普通ではなかったと気づいた
たくさん失敗できる環境が
社会で生きる力を育てていく
さらに取材では、卒業生が部活動でのエピソードを話してくれました。
「私は高校3年生のとき、多くの生徒が引退するタイミングで抜けずに、自分の納得がいくまで部活動をやり切りたいと考えていました。勉強時間は限られていたので、結局、偏差値の高い大学には行けず、受験結果から見れば失敗だったかもしれませんが、生徒の情熱を大事にし、やりたいことを思い切りやらせてくれる環境は非常にありがたかったです。社会に出て、このときに打ち込ませてくれてよかったなと感じています。今振り返ると、渋幕は自分で挽回できるような力を育てようとしてくれていたのだと思うのです」
卒業生の言葉から、渋幕的自由には短期的には失敗に見えることも、長い目で見て「自分で正解にしていく力をつける」という思いが込められていると感じます。
そして、その「自由」は学校の一部分で行われているのではなく、勉強でも行事でも部活動でもあらゆる学校生活において反映されていることもわかります。
「自由」を標榜する学校は少なくないですが、一貫して生徒に委ねて、「渋幕的自由」を体現させていることは同校の大きな特徴だといえるでしょう。