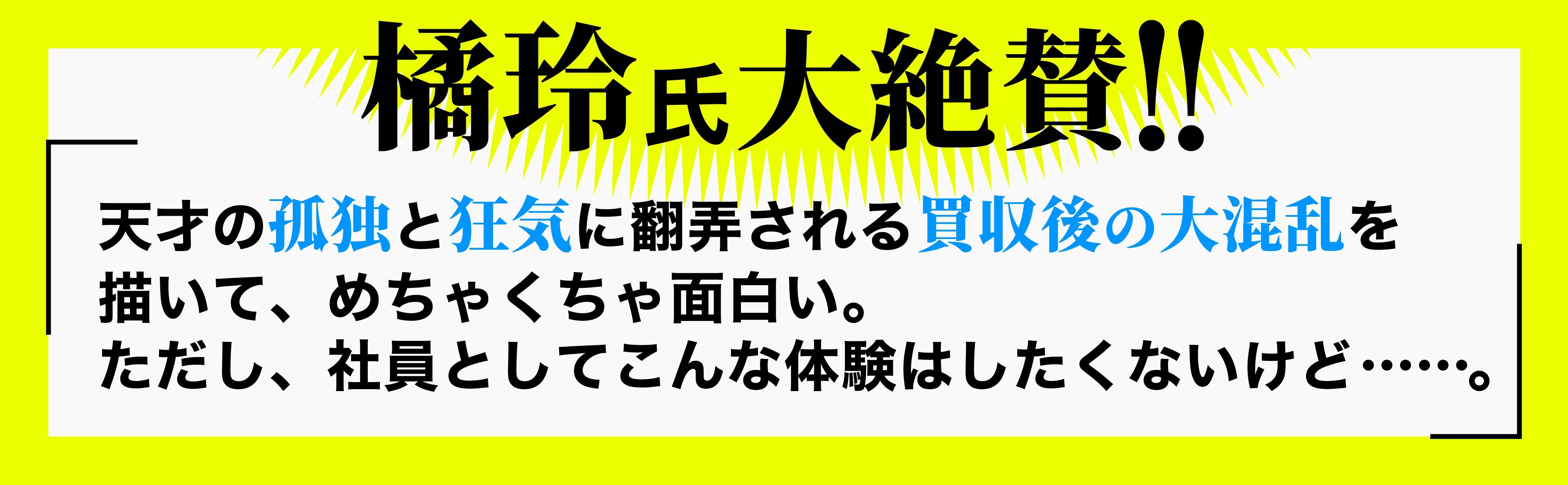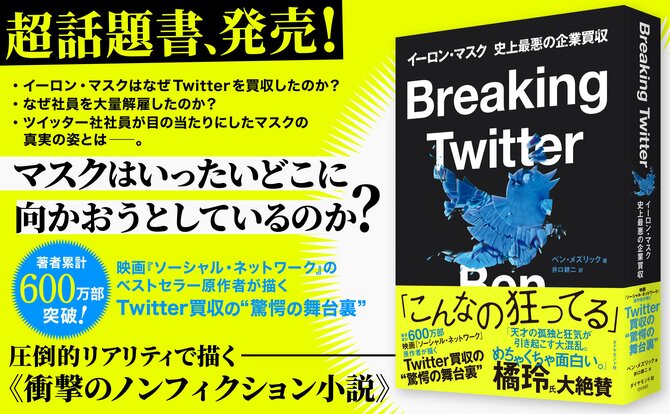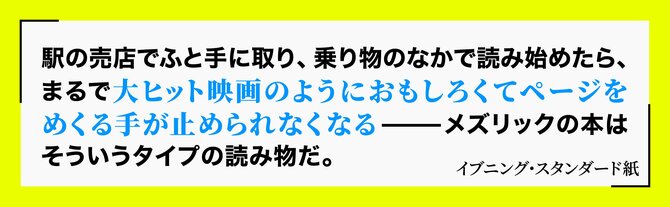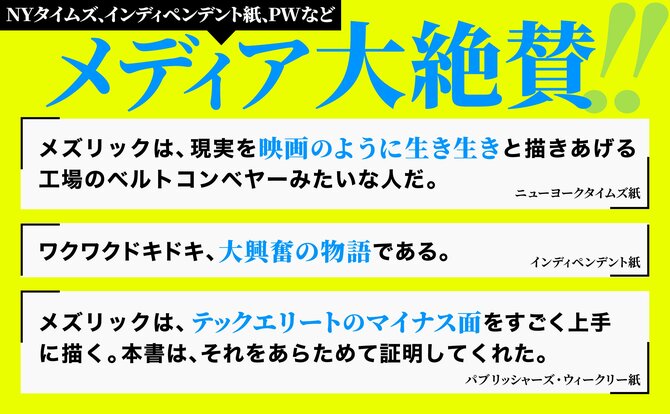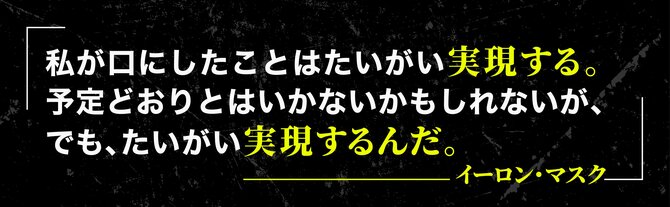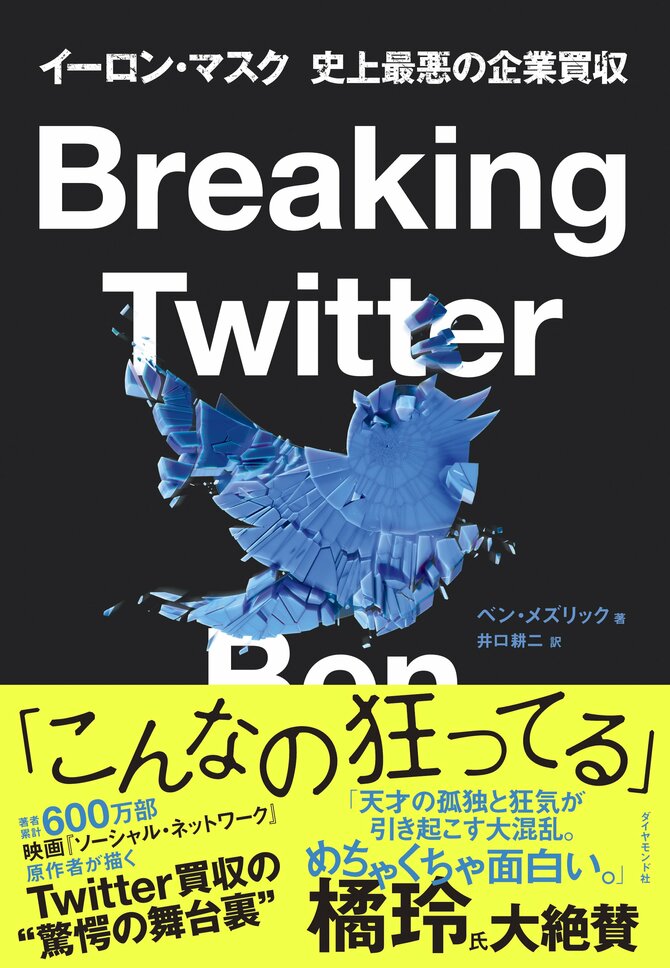買収前からTwitterのサブスクは失敗していた
マスクはツイッターの収入源をサブスクリプションに求めた。
ツイッターのサブスクリプション・プログラムはマスクの買収前から存在していた。
2021年の夏に立ち上げた「ツイッターブルー」だ。
しかし、これは収益の拡大にはそれほど貢献しなかった。その理由は2つある。
第1に、「ソーシャルメディアは無料で当たり前だ」と多くの人が思っていること。
競合のフェイスブックやインスタグラムはもちろん、インターネットなら何でも無料で手に入るイメージが定着してしまっている。
第2に、だとしたらユーザーから課金する以上、それだけの理由が求められる。お金を払っても使いたいと思うほどの機能や特徴がなければならない。
「特別な人」に無料で与えられていた「認証バッジ」を有料に
ここでマスクが目をつけたのが、「ブルーチェック」に対するユーザーの羨望だった。セレブやジャーナリスト、政治家など著名人のみに与えてきたマークだ。
ブルーチェックを手に入れた人は、自分を「特別な人」だと思わせることができる。
マスクは、この重要人物である証のマークとツイッターブルーを一つにまとめようと考えた。
当初、マスクはブルーチェックの価格を月20ドルにしようとした。しかも、前払いの年契約のみだ。
それまで無料で使っているプラットフォームに240ドルを払えというのはいくらなんでも無理がある。
ところが、「iPhoneを持っている人なら、ツイッターに年240ドルを払うぐらいどうということはない」とマスクはたかをくくっていた。
著名人からの猛反発。「なりすまし」続出で大混乱
もちろんこのアイディアには反論が殺到した。
高名な小説家のスティーブン・キングは「いままでどおりブルーチェックをつけたければ、月20ドル払えって? おとといきやがれ。逆にこっちが払ってもらってしかるべきなんだ」と反論した。
――キングなどの著名人にしてみれば、自分たちがコンテンツを提供しているからTwitterに人が集まっているというようなものだった。
マークをつけるから金を払えと言ってくるなど、ありえないことだった。
最終的にツイッターブルーは月7ドル99セントになった。
開始早々ツイッターブルーはなりすましの嵐を巻き起こした。お金で買ったブルーチェックと従来のブルーチェックを見分けられない。
ということは、偽アカウントと本物の企業アカウントやセレブアカウントを見分けられないということになる。
マーケティングや営業など、広告主と関わる人々から次々と悲鳴の電話が入り、さすがのマスクも考えを改めざるをえなくなった。
Twitter改革がうまくいかないのは、「人の気持ちがわからない」から
かくしてツイッターブルーを基軸とするサブスクリプション路線は暗礁に乗り上げた。
考えてみれば当たり前の成り行きだ。
「人の気持ちとその集積でできあがっている人間の世の中がマスクにはわからない」ということをよく示すエピソードだ。
私見では、現在手掛けている事業の中で、マスクの気性にいちばん向いているのは宇宙事業のスペースXだろう。
なぜなら、宇宙にロケットを飛ばすのは科学や工学で完結した仕事だからだ。人の気持ちを慮る必要はない。
トランプ政権への関与。テスラのブランドまで傷ついた
では、電気自動車のテスラはどうか。
最先端の製造技術や材料技術に立脚するものづくりだが、従来の自動車と同様にB to Cの商売であることに変わりはない。
モノとして優れているだけでは十分ではない。
消費者の気持ちを理解し、消費者を惹きつけなければ強いブランドを構築できない。
今年に入ってからトランプ政権の中枢に入ったマスクは(ほとんどの人が予想した通りの)大迷走を繰り広げ、テスラのブランド価値は大きく毀損した。株価もまた大きく下げた。
ツイッターは「人間の感情そのもの」。マスクには扱えない
ツイッターは「人間の感情の塊」のような商売だ。
本来、マスクにはもっとも向いていないタイプの事業と言ってよい。
そこにマスクはフルスロットルで突っ込んでいった。
本書の副題にあるように「史上最悪の企業買収」となるのは当然の成り行きだった。
(本書は『Breaking Twitter イーロン・マスク 史上最悪の企業買収』に関する書き下ろし特別投稿です)
経営学者。一橋大学特任教授(PDS寄付講座・競争戦略およびシグマクシス寄付講座・仕事論)
専攻は競争戦略。著書として『楠木建の頭の中 戦略と経営についての論考』(2024年、日本経済新聞出版)、『絶対悲観主義』(2022年、講談社)、『逆・タイムマシン経営論』(2020年、日経BP、杉浦泰氏との共著)、『ストーリーとしての競争戦略:優れた戦略の条件』(2010年、東洋経済新報社)などがある。