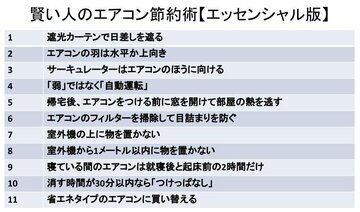写真はイメージです Photo:PIXTA
写真はイメージです Photo:PIXTA
熱中症で救急搬送されたケースの
約4割は住居内で起きている
毎年のように記録的猛暑という言葉が繰り返され、「異常気象」はもはや日常の言葉となった。気象庁が6月下旬に発表した3カ月予報について、日本気象協会は、2025年の夏も厳しい暑さとなり、9月以降も厳しい残暑が続くと解説している。もはやこの酷暑こそが、日本の夏の新たな常識なのだと認識を改めるべき時期に来ているのかもしれない。
酷暑の中、過酷な外気から身を守り、心身を休める安らぎの場、それが私たちの「住まい」であるはずだ。だが、その聖域ともいえるはずの家が、実は熱中症の主な発生場所になっているという事実をご存じだろうか。総務省消防庁のデータによれば、2024年5月から9月に熱中症で救急搬送された人の数は9万7578人にのぼり、そのうち実に38%が住居(敷地内の庭や畑などを含む)で発生していた。搬送者の多くは高齢者だが、これだけの酷暑では子どもや若者世代も決して無関係とは言えないだろう。
こうした状況を受け、建物の省エネ性能を高める動きも加速している。2025年4月からは、建築基準法の改正により、すべての新築住宅で断熱性能の基準適合が義務化された。しかし、この変化の裏側で、新築戸建ての施工現場では大きな混乱が拡大しているのが実情だ。
基準が強化されたにもかかわらず、なぜ現場では混乱が生じ、かえって施工不良のリスクが懸念される事態となっているのだろうか。その原因は、住宅の性能を左右する、いくつかの根本的な要因に隠されている。