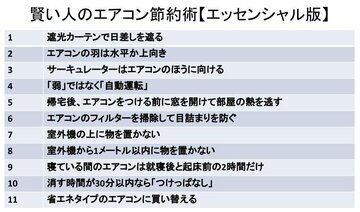例えば、報告される不備には壁や天井裏に敷き詰められる断熱材の「すき間」がある。このすき間に関しては明確な基準がなく、職人や現場監督の感覚に委ねられがちになる。そのため看過できないほどのすき間が残ってしまい、そこが熱の出入り口となってしまうケースも少なくない。また、窓の上の小さな壁や、1階より2階がせり出している部分の床下など、見落とされやすい箇所で断熱材の入れ忘れが発生することもある。
さらに専門的な問題として、気流止めの施工不備も指摘されている。気流止めは、壁の中を空気が自由に移動しないようにするための仕切りで、夏場には60℃にもなる屋根裏の熱気が、間仕切り壁の中を伝って室内に侵入するのを防ぐ重要な工程にあたる。この気流止めの入れ忘れや、すき間のある不完全な施工も、指摘の多い不備の一つだ。
こうした断熱・気密の施工不良は断熱欠損と呼ばれ、熱の通り道となり、外の熱が室内に入り込みやすくなるため、結果として冷房の効率にも影響し、室内での熱中症リスクを高める一因ともなり得る。
では、なぜこれほど多くの新築住宅で、このような施工不良が見過ごされてしまうのだろうか。その背景には、2025年4月の法改正が、皮肉にも現場の混乱を招いているという実情がある。
省エネ基準強化の裏で
施工現場が直面する課題とは
断熱基準が強化されたことは、本来、住まいの品質向上に繋がるはずだ。しかし、その過渡期である現在、むしろ現場の混乱を招き、施工不良のリスクを高めるという皮肉な構図が生まれてしまっている。
背景には、法改正という過渡期ならではの状況がある。基準の引き上げに伴い、より高性能な断熱材が使われるようになったが、その新しい施工方法に現場全体が習熟するには、まだ時間が必要な側面もあるようだ。また、耐震性や防水工事と比較すると、断熱の施工品質をチェックする体制の整備が今後の課題となっている会社も少なからず見られる。
こうした要因から、基準の高度化に現場のノウハウが追いつくには、まだ少し時間がかかると考えられるのだ。
建築業界が抱える過渡期的な課題に対し、一個人が直接働きかけることは難しいかもしれない。しかし、自らの住まいが抱えるかもしれないリスクを理解し、日々の暮らしの中で備えることは可能だ。特に、命に関わる熱中症のリスクが高まる夏場において、自宅の状態を正しく把握し、適切に対処する視点が重要になる。ここからは、ご自身で実践できる3つのチェックポイントを紹介したい。