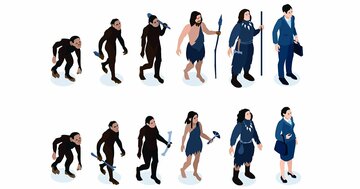それが徐々に減ってきて、現代ではほぼ座っている生活が中心となり、腰痛、肩こり、消化不良、視力・筋力の低下、運動不足による自律神経の乱れ等々、枚挙にいとまがないくらい多くの身体的な「負荷」が、かかっています。これらは当然、死との距離を縮めます。
また、死に方も変化します。体を使っている時代は、野生の動物と同じように心臓や血管など循環器系の消耗によるトラブルでピンピンコロリと死んでいました。
今は心臓への負担が減って長生きになった分、循環器以外の臓器の衰え、たとえば認知症やがん、多臓器不全などの「病気」で亡くなる割合が増えました。700万年間、人類が一番嫌っていた「孤独」と「病気」に苦しむヒトの割合が増えているのです。
つまり「幸せ」は確実に減っているのです。特に都市部でその傾向は顕著です。
連絡網すら作れない社会が
人とのつながりを断つ
「幸せ」が減った代わりに何を得たのかというと、財産を守るという観点から、プライバシーや個人の権利は強く保護されるようになりました。コミュニティが弱体化し、仲間に守ってもらえない分、法律によって保護されます。
もちろんこれは必要なことですが、一方で、ヒトとヒトの距離を縮めにくくなったり、お互いに知り合いになりにくくなったという側面もあります。
他人にあまり興味を持ってはいけなくなったとも言えるかもしれません。これは遺伝子に刻まれた、つまり進化の過程で獲得した、仲間との絆で「幸せ」を感じる性質とは矛盾します。
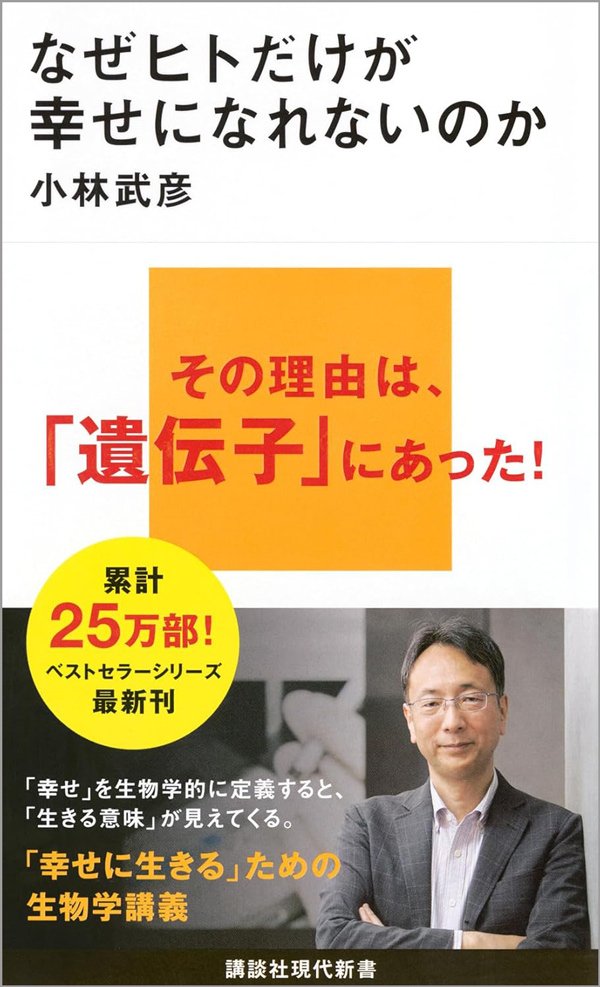 『なぜヒトだけが幸せになれないのか』(小林武彦、講談社)
『なぜヒトだけが幸せになれないのか』(小林武彦、講談社)
この個人情報の少し過剰な保護とも関係するのですが、自然災害大国日本にとってはもっと不都合なことがあります。
実際によくある話ですが、災害で行方不明になっている可能性がある方の氏名を公表しない場合があります。これは個人情報保護の観点からのことですが、誰が本当に行方不明になっているか、あるいはただ連絡がとれないだけなのかわからず、捜索の効率に影響を及ぼします。災害時に重要な学校の連絡網も今は簡単には作れません。
もう一度、個人情報の保護とはいったい何を守るためにあるのか、私たちが一番に守らなくてはならないものはなんなのかを、しっかり考える必要があります。