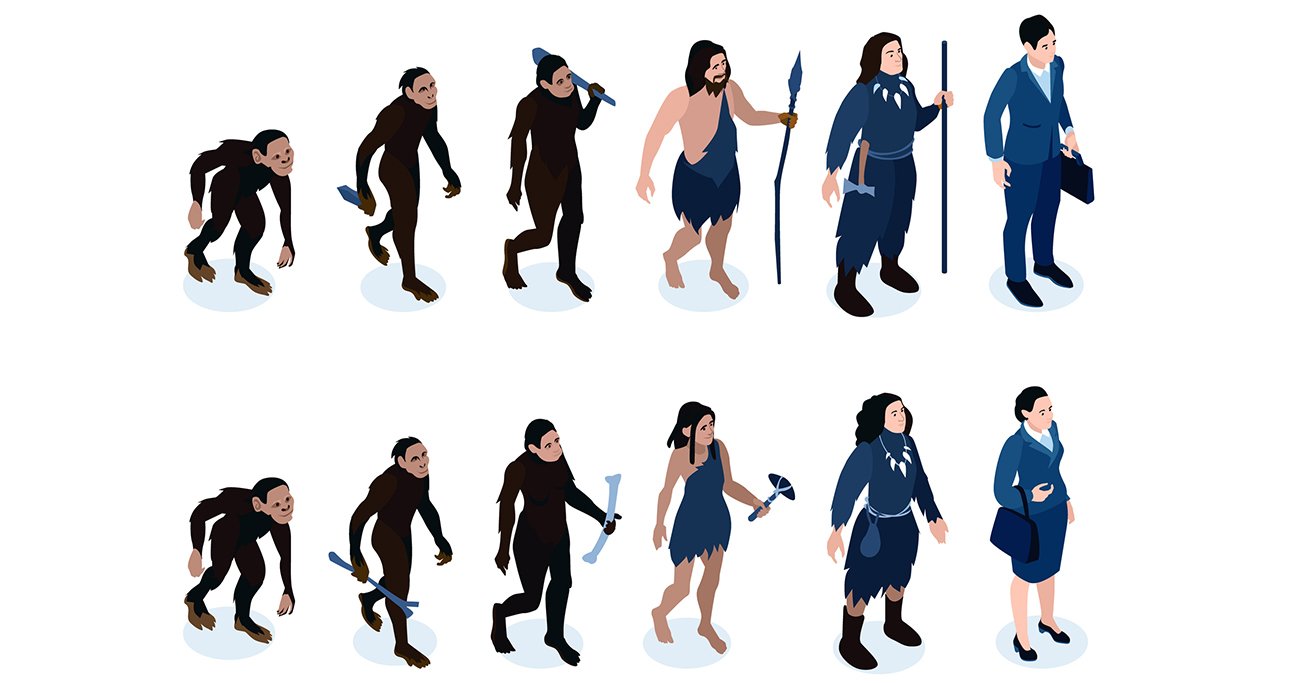 写真はイメージです Photo:PIXTA
写真はイメージです Photo:PIXTA
17世紀イギリスの哲学者ホッブズは言った。国家や法律のない自然状態における人間は、「万人の万人に対する戦い」から逃れようと、国家を作ったと。18世紀フランスの啓蒙思想家ルソーは言う。自然状態の人間は平和であり闘争がなかったが、私有財産を持ち始めることで不平等が生まれ、強者が弱者を抑圧するルールとしての法律ができたと。いま広く流布されている人類史はほとんどが彼らの著作の延長上にあるものだが、人類学者と考古学者による世界的な大ベストセラーによれば、そうした議論は科学的に間違いだという。では真の人類史とは?本稿は、デヴィッド・グレーバー、デヴィッド・ウェングロウ『万物の黎明 人類史を根本からくつがえす』(光文社)の一部を抜粋・編集したものです。
私たちはいったい何者なのか?
ほとんどが闇に埋もれた人類史
いうまでもなく、「ビッグ・ヒストリー」は、ここ最近の売れ線である。ハラリ(※編集部注、『サピエンス全史 文明の構造と人類の幸福』の著者)、ジャレド・ダイアモンド(同、『銃・病原菌・鉄』)、スティーヴン・ピンカー(同、『暴力の人類史』)などなど。かれらの本はどれも専門家の関心を超え、国際的ベストセラーとなって、世界中の書店に並んでいる。これはなにを意味しているのだろう?
おそらく、だれもがじぶんたちの生きている現在を世界史の転換点、ひょっとすると世界史(人類史)のトータルな消滅をすら予感しているといったような感触がひとつ。それにくわえて、DNA解析などの諸技術の急速な発展による、考古学/人類学領域の新発見の続出がひとつ。どうも、わたしたち人類の歴史は大きく書き換えられているようだ。
それはだれもがニュースに接していれば薄々感じるところだろう。いったいそれがわたしたちの過去をどう変貌させているのか?わたしたちはいったい、なにものなのか、本当はどこからきたのか、そしていったいどこにむかっているのか?
人類史のほとんどは、手の施しようもなく、闇に埋もれてしまっている。なるほど、われらがホモ・サピエンスは、すくなくとも20万年前から存在している。だが、いったいその20万年のあいだになにが起きていたのか、わたしたちにわかっているのは、ごくごくわずかの期間にすぎないのだ。
たとえば、スペイン北部のアルタミラ洞窟では、紀元前2万5000年から前1万5000年のあいだ、すくなくとも1万年以上かけて絵画や彫刻が制作されている。おそらく、この時代にも、たくさんのドラマティックな出来事が起きたはずだ。ところが、それがどんな出来事だったのか、わたしたちはほとんどなにも知らないのである。
もし人類史にまつわる大きな問いが浮上してくるとしたら、ふつう、人がこう自問をするようなときである。どうして世界はこうも混乱しているのか、どうして人間はかくも傷つけ合うのか、どうして戦争や貪欲、搾取があるのか、どうして他者の痛みに対する徹底した無関心がはびこるのか。わたしたちは太古の昔からそうだったのか、それともどこかの時点でなにかひどくまちがってしまったのか?
人が先史時代から教訓をえようとするとき、ほとんど例外なく、この種の問いに舞い戻ってくるのだ。
なかでもなじみ深いのは、かつては無垢な状態で暮らしていた人間が、あるとき原罪によって汚染されてしまったという、キリスト教による解答である。人間は、神のごとき存在にならんと欲し、そのために罰を受けた。いまや堕落の状態にありながら、将来の救済を待ち望みながら生きている、といった具合だ。
ジャン=ジャック・ルソーは、1754年に『人間不平等起源論』という著作を執筆したが、まさにこの著作のアップデート版の数々こそ、いまこのストーリーを普及させている主役である。
むかしむかし、わたしたちが狩猟採集民だった頃。人類は、大人になっても子どものように無邪気な心をもち、小さな集団で生活していました。この小集団は、平等でした。なぜなら、まさにその集団がとても小規模だったからです。
この幸福なありさまに終止符が打たれたのは、「農業革命」が起き、都市が出現したあとのことでした。これが「文明」と「国家」の先触れでした。「文明」や「国家」のもとで、文字による文献、科学、哲学があらわれました。
と同時に、人間の生活におけるほとんどすべての悪があらわれました。つまり、家父長制、常備軍、大量殺戮、人生の大半を書類の作成に捧げるよう命じるいとわしい官僚たちなどなどです、と。
もちろん、これはとても乱暴な単純化ではある。とはいえ、産業心理学者から革命的理論家までのだれもが、「しかし、もちろん人類は、その進化の歴史の大部分を10人か20人の集団で暮らしていた」とか「農業はおそらく人類の最悪のあやまちだった」などといった発言をするたびに、浮上してくる基本的ストーリーが、おおよそこれなのだ。
人類は文明によって抑圧されている?
その主張は正しいのか?
1651年に公刊されたホッブズの『リヴァイアサン』は、多くの意味で、近代政治理論の基礎となった書物である。人間が利己的生物である以上、初源的自然状態での生活はけっして無垢なものではなく、「孤独でまずしく、つらく残忍でみじかい」もの――基本的には、万人が万人と争い合う戦争状態――であるはずだ。
ホッブズ主義者なら、こう論じるだろう。この悲惨な状態から進歩があったとすれば、それはおよそ、まさにルソーが不満を抱いていた抑圧的機構――すなわち政府、裁判所、官僚機構、警察――のおかげであった、と。
この考え方によれば、人間社会は人間の卑しい本能を集団で抑圧することで成り立っているのであり、多数の人間がおなじ場所で生活しているようなとき、そんな抑圧がいっそう必要になる。それゆえ、現代のホッブズ主義者は、以下のように主張することになろう。
なるほど、人間は進化の歴史のほとんどを小集団というかたちで生存してきた。そしてその小集団は、主に子孫を残すという関心事を共有するおかげで、いっしょにやっていくことができた。
ところが、このような集団も、けっして平等を土台としていたわけではない。ここにはつねに、「ボス男性」(アルファ・オス)であるリーダーが存在していた。ヒエラルキーと支配、そしてシニカルな利己主義が、つねに人間社会の基礎だったのだ。
とはいえ、集団として短期的な本能よりも長期的な利益を優先するほうがじぶんたちの有利になる、もっと正確にいえば、最悪の衝動を経済のような社会的に有用な領域に限定し、それ以外の場所では禁じることを強制する法をつくることが、じぶんたちの有利になると学んできたのだ、云々。
だが、これらの議論は、人類史の一般的な流れを説明するものとしては、
1、端的に真実ではない。
2、不吉なる政治的含意をもっている。
3、過去を必要以上に退屈なものにしている。
考古学、人類学、そしてその他の関連分野で蓄積された証拠(エビデンス)は、おおよそ過去3万年のあいだに人類社会がどのように発展してきたかについて、まったくあたらしい切り口から照明を当ててきた。
いま浮上しはじめている世界像がこれまでのものとどう異なっているか、ちょっとだけ紹介してみよう。農耕開始以前の人類社会が平等主義的な小集団にとどまっていなかったことは、いまやあきらかである。
それどころか、農耕開始以前の狩猟採集民の世界は、大胆な社会的実験の世界でもあり、進化論のような貧しい抽象の提示するイメージより、政治形態のカーニヴァル・パレードこそふさわしいといった具合である。







