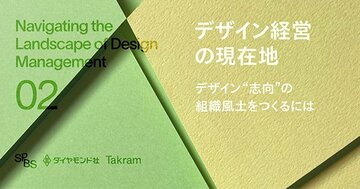デザインを手段として
ゼロイチの事業を生み出してこそ「真のCDO」
――デザインは売り上げで評価できる、と言い切るCDOは珍しいですね。
いわゆる一般的なCDO像とはちょっと違う道を行っているのでは、という自覚はあります。ひょっとするとキャリアの最初から、デザイナーとしてこうあるべき、という意識が低かったせいかもしれませんが(笑)。
――そうなんですか。
芸大(大阪芸術大学)を出てウェブデザイナーになったのも、取りあえずウェブデザインなら飯を食えるかな、程度の意識だったので……。若手の頃も「これを売りたい」とか、「事業メンバーに喜ばれたい」みたいな気持ちの方が強かったですね。デザイナーとしてようやく自信が持てたのも30代半ばで、山崎(注:前CDOで現CPO<チーフ・プロダクト・オフィサー>の山崎聡氏)と一緒に電子カルテ<エムスリーデジカル>を作ったときですから、すごく遅いんです。
――最初から、「デザインはビジネスの手段」という考え方に抵抗がなかったということですか。
そうですね。もっとさかのぼると、父が商売人だったことが原体験として大きいかもしれません。飲食店を複数経営していて、日々売り上げなどの数字を気にしているのを身近に感じて育ってきました。
今の若い世代のデザイナーたちには、当時の私とは違って「デザインで社会課題を解決したい」という理想を持っている人がとても多いです。そういった理想を描くことは本当に素晴らしいことで尊敬します。ですが、理想を描き理想を追い掛けるだけでは、日々の仕事はうまくいきません。それをメンバーにしっかり伝えることは、CDOとしての責任だと思っています。
――エムスリーに、CDOというポジションができたのは20年ですね。
はい、20年10月です。初代CDOには先にも触れた山崎が就任し、半年後に私が就任しました。CDOという役職ができた当時、私はデザイングループのリーダーでしたが、CDOになるのはまだ早いと思ってましたね。
――当時は、なぜ「早い」と判断したのでしょうか。
経営が何たるかを分かっていなかったんですね。事業を推進した経験はありましたが、経営となると決断の種類や大きさも全然違う。山崎は既にエムスリーの役員でしたから、彼の背中を見て学ぶ期間が必要でした。まあ、CDOになった今でも、まだ「真のCDO」になれたとは思っていませんが。
――「真のCDO」とは、どのようなものでしょう。
山崎はエンジニア出身ですが、経営者の一人としてデザインの重要性を理解しているし、CDOだけでなく他の事業責任者もできる人です。一方、私はデザイナー出身なのでデザインのプロセスや品質を細かく見たり、デザイン組織をリードしたりすることはできますが、事業や経営の理解はまだまだです。デザイン以外の領域で事業責任者をやれるかというと難しい。
やはり、エムスリーの柱になるような事業をゼロイチで開発する、事業責任者として事業をスケールさせる、といった経験が必要だと思っています。「デザイナー出身だし、そこまでは……」って逃げたくなる気持ちも正直ありますが、CDOを名乗る以上、事業作りを通じて経営を成り立たせることができる人物でありたいですね。