中学受験でも過酷な勉強や親のプレッシャーから、抜毛症になったり、燃え尽きて不登校になる子もいると聞きます。
好きを極めた人が活躍する時代に、嫌いなことに時間と労力を費やすほどムダなことはありません。本人が続けてみたいと思っているかどうか、親から見てわかるはずですので、向いていなければあきらめる勇気も大切です。
子ども時代の「夢中」が
人生の軸になることも
ここで間違えてほしくないのは、あきらめるべきは子どもより親のほうということです。
「アンコンシャスバイアス」(編集部注/無意識の偏見や思い込み)の中でも、教育において特に強くなりやすいのが「サンクコストバイアス」(編集部注/すでに支払って回収できない費用を惜しみ、非合理的な判断をしてしまう心理現象)です。
過去に投資した費用、労力、時間がもったいないと考え、無理に子どもに嫌がることを続けさせてしまう傾向があります。
私の息子は保育園から続けていた英語と料理教室は好きで続け、小学3~4年生のときは本人の希望でスイミングやプログラミング教室をやめました。
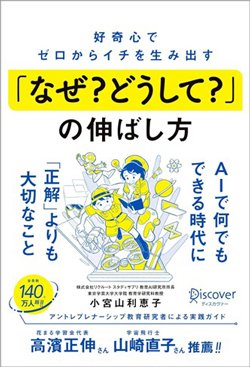 『好奇心でゼロからイチを生み出す「なぜ?どうして?」の伸ばし方』(小宮山利恵子、ディスカヴァー・トゥエンティワン)
『好奇心でゼロからイチを生み出す「なぜ?どうして?」の伸ばし方』(小宮山利恵子、ディスカヴァー・トゥエンティワン)
その後はゲームに夢中になりましたが、中学2年生のときに「ゲームはむなしい。勉強のほうが生産性があるから、僕はこれから勉強をする!」と自発的に方向転換しました。
息子はゲームを「むなしい」と表現しましたが、私自身はゲームにも生産的な側面があると思っています。ただ、それを見極め子どもに伝えるには、親自身がゲームについて理解しておく必要があるでしょう。
子ども時代に、時間を忘れるほど何かに夢中になった経験があると、次に新しい好奇心が生まれたときも同じような感覚で集中してやり抜けるようになります。
嫌なことはさっさとあきらめる。好きなことはとことんやり抜いてみる。
子ども時代にこれを経験するかしないかで、その後の人生も変わると思います。







