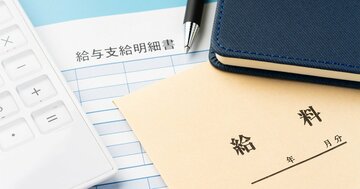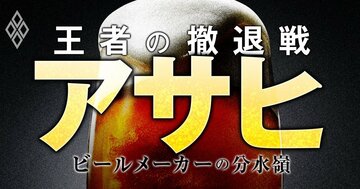リベンジ退職が企業に与える2つの重大ダメージ
リベンジ退職とは、職場での不満や負の体験への対抗措置として、社員が意図的に会社にダメージを与える形で退職する行動を指します。米国では「Revenge Quitting」と言われ、職場への不満が頂点に達したときに退職によって仕返しする行動としてトレンドとなっており、この現象が日本でも増えているようです。
例えば今年1月には、LED大手企業の元従業員が、退職の際に業務データを意図的に無断で削除したとして、会社が損害賠償を求めた裁判がありました。地裁は元従業員に約577万円の支払いを命じましたが、いずれにしてもリベンジ退職は企業に対して深刻な影響を及ぼす可能性があります。
まず、リベンジ退職の典型的なパターンとして、業務の引継ぎを拒否する、または不完全な形にしておくことがあります。現在進行中の案件を引継がない、重要な引継ぎ事項を伝えない、マニュアルを残さない、過去データを削除するなど、後任者が業務に支障がでるような状態を意図的に作り出して会社にダメージを与えようとします。
また、繁忙期を狙って突然退職するパターンもあります。業務の引継ぎを考慮して1カ月以上前に退職を申し出るよう就業規則を定めている会社が一般的ですが、退職の報告と同時に残っている年次有給休暇の請求を行い、1日も業務の引継ぎを行わず繁忙期に退職することで会社にダメージを与えようとするパターンです。
普段から退職者が出た場合を想定して、業務が属人的にならないように工夫している会社は問題ないかもしれません。しかし、たいていの会社がそう、うまくはいっていません。そのためリベンジ退職をされると、後任者は今まで抱えていた業務にプラスしてリベンジ退職者の業務をゼロから行わなければなりません。
こうなると新たな長時間労働の問題、そして著しい生産性の低下をもたらします。何も対策しなければ、リベンジ退職者の業務を受けもった後任者もリベンジ退職をするという、最悪の負のループに陥ります。これが続くと、特に中小企業では経営不能になるリスクがあります。
もう一方の典型的なパターンは、退職後に転職サイトやSNSなどで会社の実情を暴露することです。転職サイトに実情よりも話を盛って悪評ばかりを書き込んだり、SNSで会社名や該当人物があえて分かるように投稿したりして、その会社が「ブラック企業」であると拡散することで会社にダメージを与えます。たとえ事実と異なる部分があったとしても、悪評は一度広まると、採用活動に支障が出る可能性が非常に高いです。