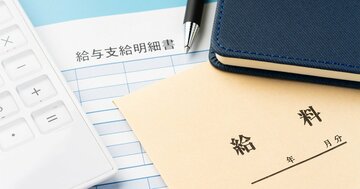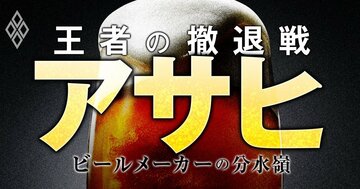原因は会社に対する不満や不信感が極めて高いこと
リベンジ退職が起きる原因は何でしょうか? まず、長期間にわたる職場の不満や、会社に改善を要望したけれど叶わなかったなどの不信感が挙げられます。将来のキャリアを計画し、理想とする職場環境で成長しようと入社を決めたものの、その願望が叶う見込みがないと感じたときにリベンジ退職を選ぶ人が多いようです。
36協定の上限を超える時間外労働が恒常化している、サービス残業を強要される、有休の取得を拒否される、パワハラ・セクハラが職場で平然と行われている、など明らかな法令違反が放置されていれば、会社に対する不満や不信感が極めて高くなるのは当然です。
法令違反はなくても、採用面接で聞いていた話と違うと感じていたり、評価制度が不透明で何をどのくらい頑張れば評価されるのかが分からない状態が続いていたり、スキルアップの機会がほとんどない職場だと、少しずつ不満や不信が蓄積されていきます。
冒頭の佐藤さんの職場の後輩のように、まだ社歴の浅い若手でも不満や不信が積み重なっていくと、「悪いのは会社だから、仕返ししてもいいんだ」といった気持ちが強くなり、リベンジ退職を誘発しやすくなります。では、企業はどのような対策をとるべきでしょうか。
リベンジ退職を防ぐための企業の2つの対策
1つ目は、評価制度の見直しです。現在の評価制度と実情が正しく運用できているか、再検討しましょう。評価制度をもとに職務内容と責任、給与を決定するのですから、実情が評価制度に基づいた正しい運用になっていることが不可欠です。
評価制度は会社が社員に対して示した約束ですので、その約束が守られれば社員は会社を信頼し、安心して成長するためのチャレンジができると感じてくれます。その会社への信頼と安心が社員の成長を促進させます。
2つ目は、採用のミスマッチをなくすことです。会社の理念を共感できない人を採用すると、価値観が合わないのでトラブルを起こしやすく、結果的に早い段階で退職する可能性が高いです。新卒入社も転職も多大なエネルギーを伴う決断であり、期待と不安が入り混じっています。大きな期待があったからこそ、裏切られたと感じた際には復讐となって返ってくるのです。
特に中小企業の場合、人手不足のため採用したい思いが強く、求人募集で実情と異なる告知をするケースがあります。しかし仮に採用できたとしても、より大きなトラブルとなって返ってきます。どんな人を採用するのか、面接者はどんな質問をするのか、どんな回答なら合格なのか、面接は何回行うのか、スキルを確認するためにどんなテストを行うのかなど、採用基準をつくることから始めるとよいでしょう。
ミスマッチのない採用をし、入社後は明確な評価制度を適正に運用していく。そうすれば、社員は成長して生産性も上がり、会社の業績を伸ばすことにつながります。もちろん、リベンジ退職に怯える必要もないでしょう。