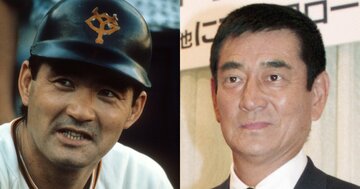写真はイメージです Photo:PIXTA
写真はイメージです Photo:PIXTA
スマホもパソコンもなかった時代、テレビは茶の間の主役であり、“家電”を超えた存在だった。木目調の筐体、大げさな商品名、家族のチャンネル争い、そして過剰とも言える演出の数々。昭和のテレビには、無茶苦茶なのに不思議と元気と勢いがあった。今では考えられない“日常の風景”を、もう一度振り返る。※本稿は、葛城明彦『不適切な昭和』(中央公論新社)の一部を抜粋・編集したものです。
大袈裟な名前に購入者特典と
テレビの売り方が変だった
昭和期はまだ家電が高価だったこともあって、どの製品にもビックリするほど大げさな名前がつけられていた。
例えばテレビも、「王座」「名門」(いずれも東芝)、「薔薇」「日本」「帝王」(三洋電機※「帝王」は平成初期)、「高雄」(三菱電機)、「太陽」(NEC)、「王朝」(ゼネラル)といった具合で、それらの多くは家具調で高級感のある木製フレームに収まっていた。また、そうしたテレビは、今とは比べ物にならないほど大切に扱われていて、みない時にはビロードの覆いをかけたりする家庭も多かった。
なお、テレビに関してはCMもまた大げさで、1965(昭和40)年の「嵯峨」(松下電器)など、「日本伝統の優雅な美しさを見事に盛り上げたナショナルテレビ『嵯峨』。ウォールナットの肌合いを生かしたデザイン。黄金シリーズの高性能。ナショナル人工頭脳テレビ『嵯峨』は……」といった調子であった。
大手メーカーではテレビ購入者に景品をつけていたこともあって、一時期は「黄金の茶釜」(松下電器)、「維新の大砲」(日立)、「幸福を呼ぶ十二支の置物」(東芝)などで競い合っていた。