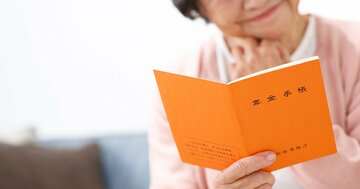中古車市場で質のよい中古車を手に入れられないですし、長生きの人が私的年金に入ろうとしても有利なものはなくなっているのです。そのため、長生きリスクに備えるための年金制度は、強制加入にして、国民に義務づけないとうまく機能しないのです。
採用で学歴を重視するのは
情報格差を埋める企業の工夫
学歴も情報の非対称性を克服するための仕組みと考えられています。企業のように人を採用する側には、応募してきた労働者の質はわからないものです。時給2000円で従業員を募集した場合、2000円もらえば働きたい人全員が応募してきます。
しかし、その中には、時間あたり2000円分の価値のある仕事ができない人も多く含まれます。レモン市場がここにも発生します。どうすれば、優秀な人に高い賃金を払って、そうでない人には低い賃金を払うということができるのでしょうか。
1つの方法は、採用側が応募者にある資格を取ってもらうことを採用の条件にすることです。その資格は、優秀な労働者には簡単に取れて、優秀でない労働者には苦労しないと取れないとします。
 『経済学者のアタマの中』(大竹文雄、筑摩書房)
『経済学者のアタマの中』(大竹文雄、筑摩書房)
その資格を取ったところで労働者の生産性は変わらないものの、優秀な労働者にとって、その資格を取ることは自分が優秀であることを採用側に示すことになります。
この資格は、労働者の生産性の高さを示すシグナルになるのです。採用側が大学卒業を条件にするのは、学歴をシグナルに使っているというのです。
この考え方は、シグナリング理論と呼ばれ、1973年にマイケル・スペンス教授が論文を発表しました(Spence, 1973)。アカロフ教授とスペンス教授は2001年にノーベル経済学賞を受けています。
教科書も存在しないほど新しい分野について、出たばかりの学術論文などを読んで最先端の研究のことを学びながら、情報の非対称性があると市場経済がうまく動かないと理解していくことは、大学生だった私にとって非常に刺激的でした。