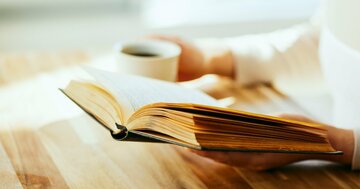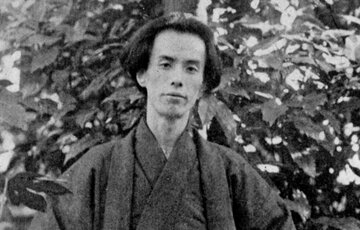このことについて、村上自身も次のように書いている。
関西弁に話を戻すと、僕はどうも関西では小説が書きづらいような気がする。これは関西にいるとどうしても関西弁でものを考えてしまうからである。関西弁には関西弁独自の思考システムというものがあって、そのシステムの中にはまりこんでしまうと、東京で書く文章とはどうも文章の質やリズムや発想が変わってしまい、ひいては僕の書く小説のスタイルまでががらりと変わってしまうのである。僕が関西にずっと住んで小説を書いていたら、今とはかなり違ったかんじの小説を書いていたような気がする。その方が良かったんじゃないかと言われるとつらいですけど。
(『うずまき猫のみつけかた』に所収されている一遍「関西弁について」より 文藝春秋 1996)
ではなぜ、『海辺のカフカ』では大阪人の夫婦を登場させて、大阪人のステレオタイプ的な台詞を話させたのかということについては、今ひとつよく分からないところがある。
また、上の引用における「関西弁独自の思考システム」というのがどういうことをさすのか、すぐには分からないのだが、とりあえず一旦村上春樹を離れて、関西弁を話す登場人物が受け手にどのような印象を与えるか、あるいは作り手はどのような意図で関西弁キャラを登場させるかということについて、実例に則して考えていく。なお、後に再び村上春樹と関西弁について考えてみたい。
関西弁が持つ性質は
登場人物のキャラクターを決める
私はかつて『ヴァーチャル日本語 役割語の謎』(岩波書店 2003)を著し、その後も「役割語」に関連する著作を公刊してきた。
役割語とは、主にフィクションの中で、話者のキャラクター(属性)に応じてある程度決まってくる話し方のスタイルのことである。たとえば、「そうじゃ、わしが知っておるんじゃ」と言えば老人、「そうですわよ、わたくしが存じておりますわよ」と言えばお嬢様、といった具合である。そして、方言的な表現も時に役割語となる。大阪弁・関西弁キャラがその典型である。