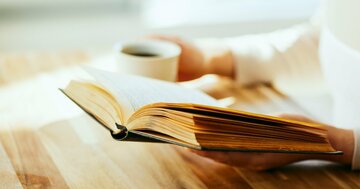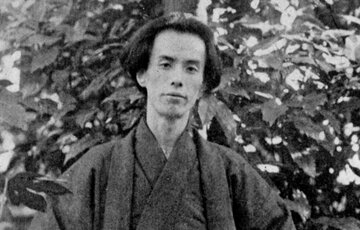『ヴァーチャル日本語 役割語の謎』では、関西弁キャラが往々にして持つ性質を次のように整理した。
1 冗談好き、笑わせ好き、おしゃべり好き
2 けち、守銭奴、拝金主義者
3 食通、食いしん坊
4 派手好き
5 好色、下品
6 ど根性(逆境に強く、エネルギッシュにそれを乗り越えていく)
7 やくざ、暴力団、恐い
これらの性質は、一度に生じたものではなく、歴史的に波状的に形成されたと旧著では考えている。すなわち、1~4までは江戸時代の上方文化(特に大坂=大阪の文化)に由来するもので、江戸の人たちから見た場合、商都大阪からやって来る人々は話し好きで、商売上手であり、食べ物や服飾等の現世的な快楽を素直に肯定する傾向が強かったところから生じたステレオタイプであったであろう。
これに対し、5の性質は、井原西鶴の「好色もの」など、江戸時代に萌芽はあったが、今日に繋がる作品としては今東光や野坂昭如の作品が強い影響を与えたかもしれない。
また6に関しては、例えば織田作之助「夫婦善哉」(『夫婦善哉・木の都』所収 新潮社 1950)の主人公・柳吉は、ど根性とは対極の人物であり、大阪人のステレオタイプとは言えない。おそらくは、花登筐(はなとこばこ)の「根性もの」が強い影響を与えたものだが、花登筐はむしろ近江商人の気質を念頭に作品を書いていたようである。
最後の7は、江戸時代には上方者は柔弱と捉えられており、むしろけんかっ早い江戸っ子の対極と思われていたフシがある。しかし人形浄瑠璃「夏祭浪花鑑」(岩波文庫 1982)などは、大阪の侠客(きょうかく)の暴力を描いており、後のやくざ・暴力団ものを先取りしていたとも見える。
しかし本格的には、今東光の『悪名』シリーズ(文藝春秋 1955~)、また1975年頃以降の暴力団映画や、『嗚呼!!花の応援団』(どおくまん著 秋田書店 1970~1979)『じゃりン子チエ』(はるき悦巳著 双葉社 1980~1997)等のマンガ作品がそのようなイメージを強化したものと思われる。