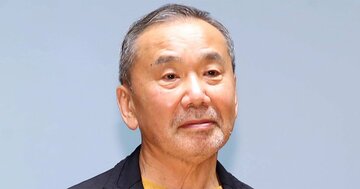Photo:SANKEI
Photo:SANKEI
秋田弁や福岡弁など、さまざまな方言がある中で、最も全国的に馴染みがあるのは大阪弁だろう。その広がりにはお笑い文化が深く結びついている。新喜劇や落語から始まり、ダウンタウンや新世代の芸人たちが言葉づかいをさらに変えていく。そうした変遷をたどると、関西弁が“みんなの言葉”になるまでのユニークな歩みが見えてくる。※本稿は、金水 敏『大阪ことばの謎』(SBクリエイティブ)の一部を抜粋・編集したものです。
お笑い文化を通して全国的な
「大阪弁ブーム」が到来
戦後、産業・経済の復興は進んだが、東京一極集中の傾向は止められず、1970年の日本万国博覧会はあったものの、経済のいわゆる「地盤沈下」が止まらないまま今日に至っていると言える。現実の大阪の町も、地盤が軟弱な上に過剰な地下水のくみ上げを行ったため、地盤が沈下して大きな問題が起こっていた。経済の「地盤沈下」はそのような状況にかけた表現であった。
その一方で、「お笑い」「食いだおれ」等に象徴される大衆文化の町としてのイメージが固定化し、お笑いを通じて大阪弁が広く国民に認知されるようになり、全国的な「大阪弁ブーム」も数次起こった。
戦後の復興期には、松竹新喜劇(1948年)、吉本新喜劇(1962年)といった商業演劇が立ち上がり、また森繁久弥主演で映画「夫婦善哉」(東宝 1955年)が上映された。
しゃべくり漫才の人気者、花菱アチャコが主演を務めたラジオドラマ「お父さんはお人好し」(朝日放送 1954年)が放送され、今東光が河内弁を用いて書いた小説『悪名』(文藝春秋 1961年)は、同年に勝新太郎・田宮二郞出演によって映画化もされた。こういった動きによって、戦前のコテコテ大阪弁や荒っぽい河内弁が戦後に受けつがれたのである。