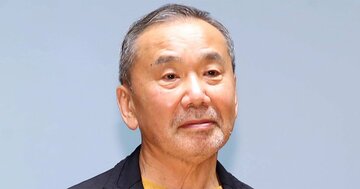大阪弁を日本全国に広めた
上方落語の人気者たち
大阪弁を日本全国に広めた立役者として、上方落語の噺家たちの活躍は大変大きいものがあった。
実は上方落語は、一度存亡の危機に立った。初代桂春團治は戦前、爆笑王の呼び声をほしいままにし、二代目桂春團治も才能は初代以上と言われていたが、1953年に58歳で急死した。上方落語界の大御所たちも次々亡くなっていたタイミングであったこともあって、もはや上方落語の将来はないと危ぶむ声が高まった。
この危機に際して力を尽くしたのが、後に「上方落語の四天王」と呼ばれることになる、三代目桂米朝、六代目笑福亭松鶴、五代目桂文枝、三代目桂春團治であった。
ことに桂米朝は古老から埋もれていたネタを聞き取りして掘り起こし、『米朝落語全集』全七巻(朝日新聞社 1980~1982年)にまとめるなど、功績があった。その活躍により、桂米朝は1996年、重要無形文化財保持者(人間国宝)に認定された。
桂米朝の師匠である桂米團治が1939年ごろに作った「代書」の一節を抜き出しておこう。コテコテ大阪弁の特徴が現れていることがわかる。
代書屋「エ──、あんたは世帯主でっしゃろな」
客「えへ、あんた、おだてなはんな」
代「誰がおだてるかいな。いえな、あんたが家の大将、ほたら世帯主や。わからん人が来たな。名前は」
客「田中彦次郎ち言いまんね。ちょっと粋な名前」
代「別に粋なことはないけどな。田中彦次郎。この彦次郎の次という字は、次という字ですか治めるという字ですか」
客「そこらはお任せ致します」
代「任したらいかんで、そんなもん。あんたの名前やで。何やわからん人が来たな」
(『米朝落語全集』第七巻に所収 朝日新聞社 1980~1982年)
明石家さんまや笑福亭鶴瓶が
テレビで大阪弁を駆使して人気に
さらに大阪弁を全国に広める役目を果たしたのは、四天王の弟子たち以降の噺家であった。ラジオの深夜番組のパーソナリティーとして、桂三枝(後の六代文枝)、笑福亭仁鶴、笑福亭鶴瓶といった面々が若者に人気を得た。ことに笑福亭鶴光は、ニッポン放送の「オールナイトニッポン」で全国放送のパーソナリティーとなり、「鶴光でおまんねやわ」(編集部注/同ラジオで使用していたキャッチフレーズ)等、意識的に古い大阪弁、つまりコテコテ大阪弁を駆使して大いに受けた。