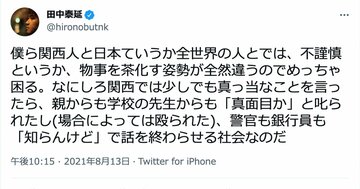写真はイメージです Photo:PIXTA
写真はイメージです Photo:PIXTA
税務署員の訪問を歓迎する者はほぼいないだろう。嫌がる相手と仕事をしなくてはならない彼らにとって、関西弁は強い味方なのだとか。大阪国税局などで活躍した職員たちが語る、納税者との信頼を築くための大阪弁コミュニケーション術とは?そこにはビジネスにも活かせそうなヒントが、たくさん転がっていた。※本稿は、札埜和男『大阪弁の深み その独特の魅力を味わう』(PHP新書)の一部を抜粋・編集したものです。
元・税務署員が語る
「大阪弁」の機能とは
「税金」を扱う行政の現場で、方言はどのような機能を持つのであろうか。関西の税務署や大阪国税局に勤務した経験を持つ、大阪府出身のZ氏にインタビューを行なった(インタビューでは「関西弁」と称したので、そのように記述しているが、「大阪弁」と言い換えても差し支えないと考えられる)。
Z氏によれば税務は他の行政サービスとは本質的に性格が異なるという。氏は納税者を「お客さん」と呼ぶ。(編集部注/以下、《》内はZ氏のコメント)
《書類不備であれば、取りに帰って、と言えるわけです。税金の徴収はそういうわけにはいきません。書類の書き方わからへんかったら教えますし、来た時に帰したらあかんのです。書類不備ですと言(ゆ)うて帰したら二度と来ません。後で払うわと言われてもいつ払ってくれるかわかれへんのです。今払わさんとあかんのです。ですから役所で一番親切です。》
《我々の手法にも『現況調査』といって任意調査はありますが(筆者注/強制調査は国税局査察部のみ)、別に捜査令状を持っているわけではないんです。任意ですから相手の同意がいるんです。お客さんの協力がない限りビタ一文取れないのです。したがってコミュニケーションの位置づけも異なります。》