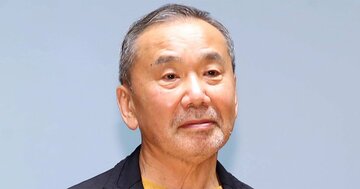テレビでは、「ヤングおー!おー!」(毎日放送 1969年~1982年 桂三枝→文枝、笑福亭仁鶴、月亭八方、桂文珍等出演)が大きな役割を果たしたが、その後も「新婚さんいらっしゃい!」(朝日放送 1971年~現在放送中 桂三枝→文枝)、「バラエティー生活笑百科」(NHK 1985年~2022年 笑福亭仁鶴)、「鶴瓶の家族に乾杯」(NHK 1995年~現在放送中 笑福亭鶴瓶)のような全国放送のテレビ番組にもこれらの噺家が出演し、大阪弁を大いに全国に届けた。
明石家さんまの活躍も見逃せない。彼の師匠は五代目松鶴の弟子の笑福亭松之助であったが、さんまは落語家にはならず、ラジオの物真似芸人、ラジオのパーソナリティー、コメディアン、テレビ番組の司会者、テレビドラマの俳優等、八面六臂の活躍をし、女優の大竹しのぶと結婚(後に離婚)するなど、大スターとなった。
「でんがな」「まんがな」を
使わない上方漫才の登場
上方漫才もまた、全国に大きなインパクトを与えた。
そのきっかけとして、1980年の「マンザイ・ブーム」があった。1980年代初頭、さまざまなメディアを漫才が席巻したのである。この時期、島田紳助・松本竜介、横山やすし・西川きよし、今いくよ・くるよ、オール阪神・巨人、ザ・ぼんち、西川のりお・上方よしお、太平サブロー・シローといったコンビが人気を得た。また1986年にオープンした心斎橋2丁目劇場(編集部注/1987~1999年に吉本興業が大阪・心斎橋で運営していた劇場)からはダウンタウンやハイヒール、トミーズ等の人気者が生まれた。
彼ら、気鋭の漫才師のことばには、もはやコテコテ大阪弁の要素は消えて、普通の市民の大阪弁に近いものが使われていた。
大阪出身の漫才コンビ、「ミルクボーイ」のネタを見てみよう。もはやコテコテ大阪弁の要素はなく、現代の大阪人のことばになっていることに注意したい。
駒場「うちのオカンがね、好きな朝ごはんがあるらしいんやけど、その名前はちょっと忘れたらしくて」
内海「朝ごはんの名前忘れてもうて、どうなってんねんそれ。でもね、オカンの好きな朝ごはんなんか、岩のりか、めかぶぐらいやろそんなもん」
駒場「それがちゃうらしいねんな」
内海「違うの、えー」
駒場「まあいろいろ聞くんやけど、分かれへんねんね」
内海「えー分かれへんの、そしたらおれがね、オカンの好きな朝ごはん、ちょっと一緒に考えてあげるから、ちょっとどんな特徴ゆうてたか教えてみてよ」