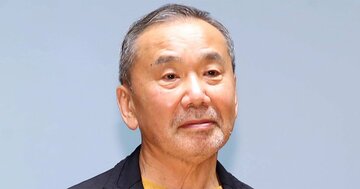ここで見られる大阪弁の特徴は、「へん」「ねん」「ゆうてた」等、関西全域で今日広く用いられている要素にほぼ限られる。
関西の一部で使われていた
「オカン」の全国化
また「オカン」という表現は、松本修氏の『どんくさいおかんがキレるみたいな。』(朝日新聞出版 2009年)でも取り上げられているように、もともと大阪の周縁部で用いられていた方言語彙で(真田信治、他著『大阪のことば地図』に基づく言語地理学的調査より)、1970年代くらいまでは大阪市内ではむしろ「お母ちゃん」のほうが優位であった。私自身も、小学生の頃は「お母ちゃん」「お父ちゃん」と呼んでいた。
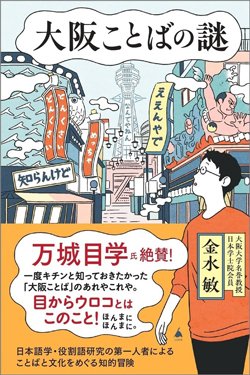 『大阪ことばの謎』(金水 敏 SB新書、SBクリエイティブ)
『大阪ことばの謎』(金水 敏 SB新書、SBクリエイティブ)
「オカン」が広まり始めたきっかけの一つを、松本氏はダウンタウンのコント・シリーズ「おかんとマー君」と見ている。これはフジテレビで1991~1997年に放送していた「ダウンタウンのごっつええ感じ」の中のコーナーである。
余談であるが、坂本龍一、テイ・トウワほか一流ミュージシャンとダウンタウンが1994年にコラボしたGEISHA GIRLSという音楽ユニットの楽曲「Kick & Loud」でも、ダウンタウンが「おとん、おかん、おねん、おにん」とラップで叫んでいる。
こういったダウンタウンの影響もあってか、「オカン」は全国化し、2005年のリリー・フランキーの小説『東京タワー──オカンとボクと、時々、オトン』(扶桑社)や、2009年のNHKの朝の連続テレビ小説「つばさ」につながったようである。
後者は埼玉県川越市に住む女子大学生・つばさ(多部未華子)が主人公であるが、彼女は自分のことを「二十歳のオカン」と称していた。このように、「オカン」は大阪弁であるとしても、広く用いられるようになったのは1990年代以降と考えてよい。