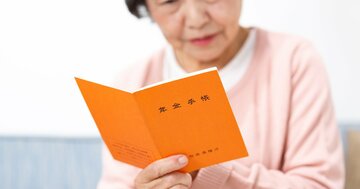もう一つは、「お金のありかの確認」だ。
金融資産の残高は聞かなくとも、お金の預け先は共有しておきたい。相続が発生したときに困るからだ。
エクセルで「金融機関名」「支店名」を埋める表を作り、パートナーに「金額は入れても、入れなくてもいいから、これだけ入力しておいて」と渡す。もちろん、自分の表も作り、相手に渡しておこう。
家族が亡くなったとき、お金の預け先がわからないと、手続きが煩雑になり地獄を見ることになることを覚えておきたい。
えっ、うちのお金これだけ!?
「高収入=お金持ち」ではない!
反対に、配偶者に先立たれたら、自分の老後資金だけで暮らしていくのは心もとないという人は、お互いの金融資産の金額と公的年金の額の共有をしておきたい。
フルタイムで働いていた期間が少ない妻、長い期間働いていても年収が多くなかった人がこれにあたる。毎年の収入が多くない場合、一人で十分な老後資金を貯めるのが難しかったりする。
配偶者の年収が高いと、漠然と「そこそこお金をもっているのだろうな」と考える人がいるが、お金というものは使えば残らない。
夫に先立たれた後に、「えっ、うちのお金これだけしかないの!」といった事態にならないように、本格的な老後を迎える前にお金事情の共有をしておきたい。
想像以上に金融資産が少なかったら、60歳以降の支出を見直す、長く働くなど対策が取れるので、先延ばしにせずに行動しよう。
公的年金の金額を共有するのは、遺族年金の金額を知っておくためだ。
夫の厚生年金の4分の3が遺族厚生年金で、自分の老齢基礎年金を合わせた金額で暮らしていくことになる。これはねんきん定期便を見せてもらえば計算できる。
もちろん、「借金の有無の確認」も忘れずに。
「定年」は、夫婦でお金の話をするとてもいいきっかけだ。このきっかけを逃さずにお金事情の共有をしてはどうだろうか。秘密のままにしておきたいと考えたとしても、亡くなると全部家族に知られることになる。
「お父さん、こんなにお金あったのに、お母さんを旅行に連れて行ったこともない」と、死んだ後に子どもたちに悪口を言われないように生前にオープンにしておきたいものだ。