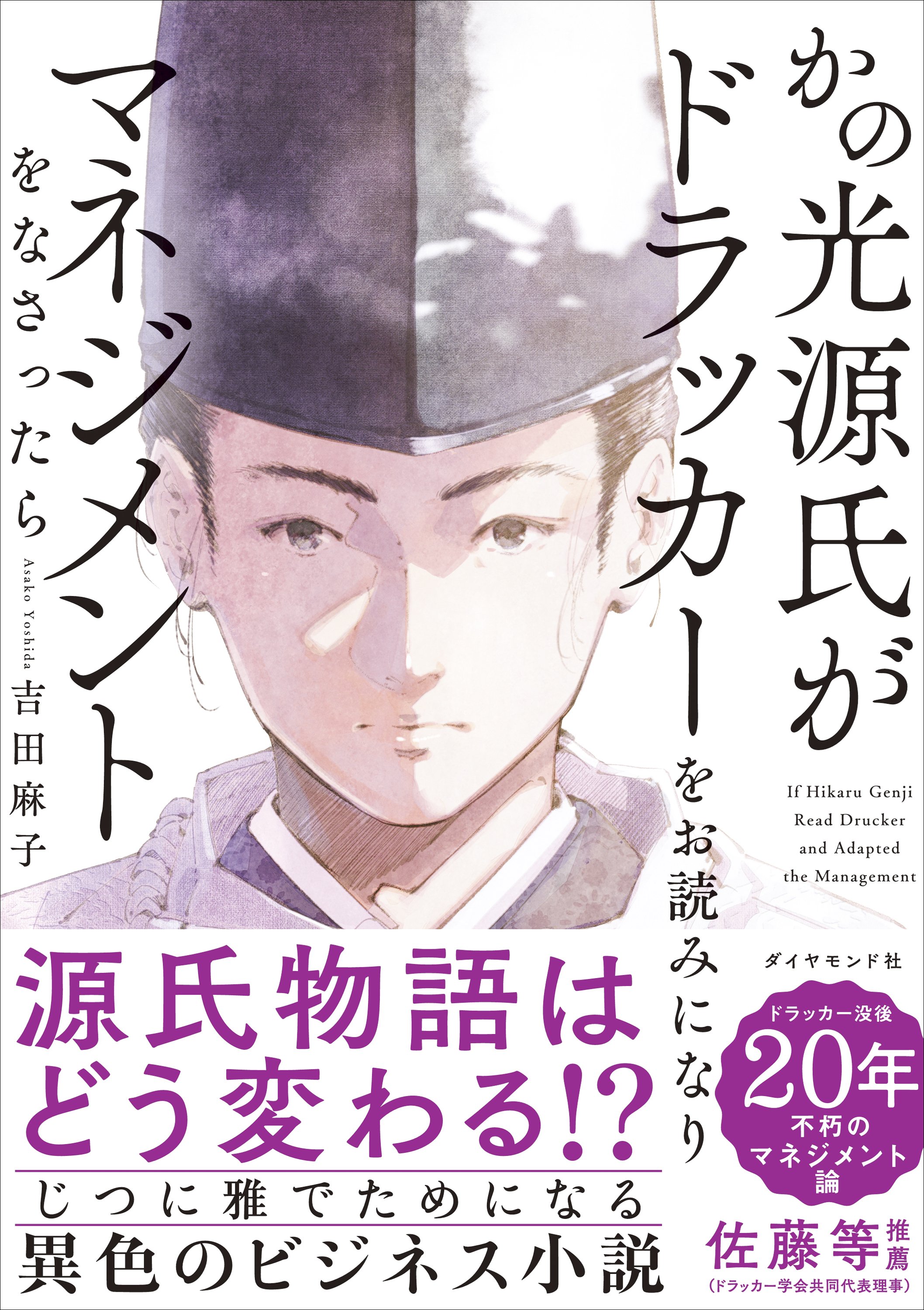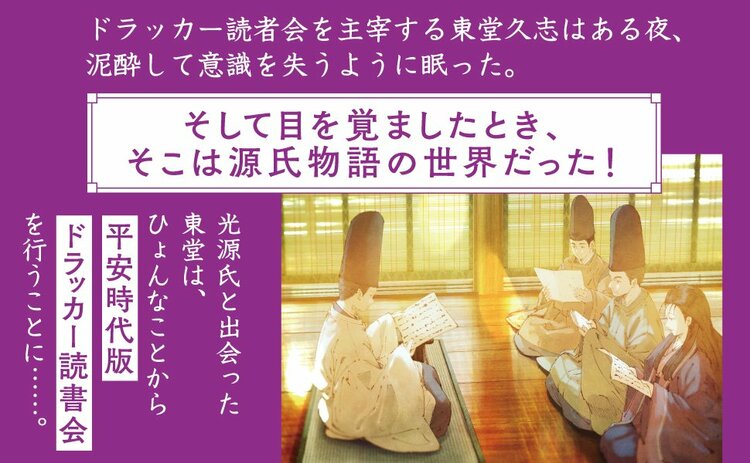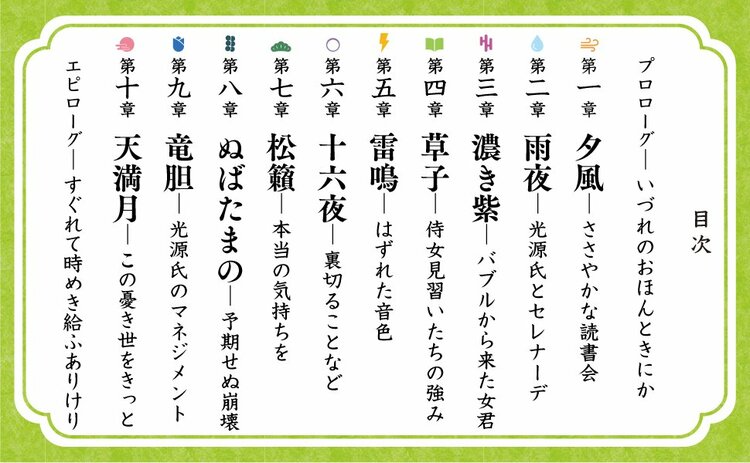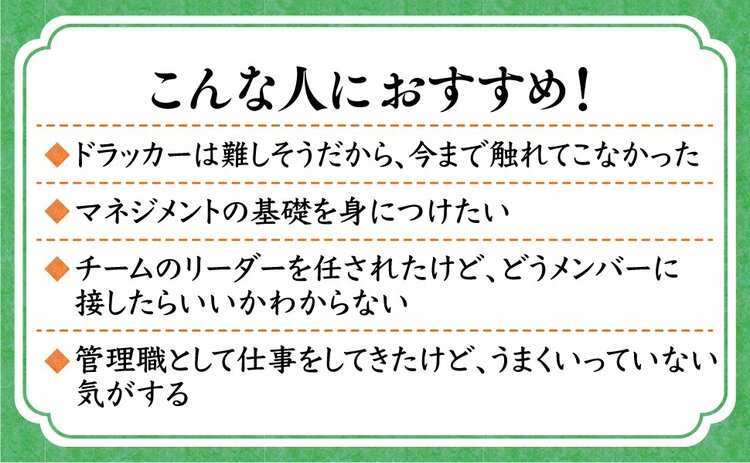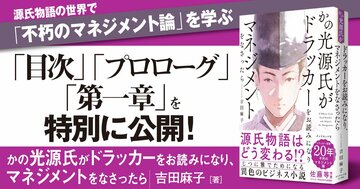「上司の強みを生かす」実践方法
――では、具体的な「上司の強みを生かす」実践方法についてご紹介していきましょう。
ドラッカーは同じく『経営者の条件』の『第四章 人の強みを生かす』でこのような文章を書いています。
「上司もまた人であって、それぞれの成果のあげ方があることを知らなければならない。上司に特有の仕事の仕方を知る必要がある。単なる癖や習慣かもしれない。しかしそれらは実在する現実である」
――具体的実践方法をいくつか提案しましょう。
◻︎上司の癖をメモする:「なんでも手帳にメモしている」、「おしゃべりが多い」、などの行動の癖以外に、口癖や仕事のパターンなどを見つけたらメモしてみましょう。感情を交えず客観的に観察をしてみましょう。
◻︎上司の推しポイントを探す:「クレーム対応のときの、思わず許したくなる困った笑顔」、「デスクの上がいつもキレイ」、「忘れ物をしても代替品でなんとかするアドリブ能力すごい」など、「ここは推せる」という部分を探すチャレンジをしてみましょう。
◻︎上司のワークスタイルを知る:「電話よりメール」、「残業より早出」、「チームより一人」、「リーダー型より補佐型」など、上司が得意な仕事の仕方はどんなものかを日々の業務の中で見つけてみましょう。
どれか一つでもやってみると、思いがけず目の前の景色が変わったように感じられ、精神的な落ち込みが穏やかな客観的モードに切り替わるきっかけになるかもしれませんね。
ここで、「仕事の仕方」という言葉ができました。これについては『明日を支配するもの』の『第6章 自らをマネジメントする―明日の生き方』の『仕事の仕方』という節を見ていきましょう。
「強みと同じように、仕事の仕方も、人それぞれである。それは個性である。生まれつきのものか、育ちのものかは別として、それらの個性は、仕事につくはるか前に形成される」
――このように「仕事の仕方」も強みと同じように大切な要素です。具体的には同書にて「聞き手か読み手か」「学び方はどうか」などと書かれています。私もかつて上司に口頭で何かを伝えてもすぐに忘れてしまうことが多く、デスクにメモを貼って伝えるようにしたらしっかり伝わるようになったことがありました。彼は読み手だったわけです。このように、上司の「仕事の仕方」を観察すると、よりよい付き合い方が見えてきます。
Aさん
「そもそも、考え方とか性格がかけ離れていてイライラする場合もあるんですが」
Bさん
「そうそう、『ありえない』って思っちゃう」
Cさん
「それってドラッカーは何か言っていますか?」
――同じく『明日を支配するもの』の『第6章 自らをマネジメントするー明日の生き方』の続きに、『価値あること』という節がありますので紹介しますね。このように書いています。
「組織には価値観がある。そこに働く者にも価値観がある。組織において成果を上げるためには、働く者の価値観が組織の価値観になじむものでなければならない。同じである必要はない。だが、共存しえなければならない。さもなければ、心楽しまず、成果も上がらない」
Aさん
「価値観か……。そうか、そもそもうちの会社の価値観について考えたことはなかったな」
Bさん
「会社と上司の価値観は、うちは一致している気がする。私もそういう意味では自分の価値観と共存できているかも。ただ、上司の弱みにイライラしているだけかも」
Cさん
「上司の価値観、自分の価値観。それぞれをちょっと意識してみようと思います」
――強み、仕事の仕方、価値観。この三つの問題に答えが出さえすれば、自分が最も力を発揮できるところに自分を置くことができるとドラッカーは言っていますが、同じ組織にいる人同士がお互いに共存できる価値観を大切にしていれば、強みや仕事の仕方は異なっていても、いや、むしろ異なっているからこそそれぞれの異なる強みを生かせる職場となっていけるかもしれませんね。
最後に、理不尽な上司対策「実践チェックリスト」をお渡ししましょう!
①上司の“推しポイント”はどこ? (強み)
②上司の“やりやすいやり方”はどれ? (仕事の仕方)
③上司の“こだわっていること”は何? (価値観)
この3つを意識すると、理不尽の裏側に「攻略のカギ」が見えてきますよ!
理不尽な上司を“攻略する”ことは、キャリアを加速させる実践トレーニングになるかもしれません。