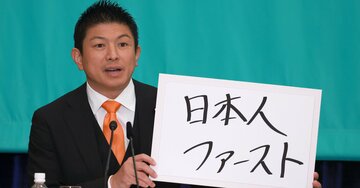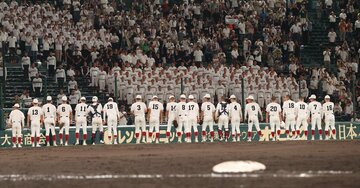今年4月、マスコミに報じられたのは大分県中津市の店舗だ。客が「まぐろの大葉はさみ揚げ」を注文して食べたところ、口の中に違和感があったので確認すると、それはまぐろでも大葉でもなく「吸水シート」だった。
7月、Threads(スレッズ)に投稿された写真で話題になったのは、茶わん蒸しの異物混入だ。投稿主によれば、フタを開けたところ茶わん蒸しの表面に「使用済みの甘だれのゴミが一緒に蒸されていた」という。
後にJ-CASTニュースが「はま寿司」側に確認したところ「食器洗浄機内において食器に付着した異物が商品の作成段階で気付かれず混入した」可能性が高いという。
そして最近起きたのが、洗剤の混入だ。
8月17日、宮城県の「はま寿司」の店舗で、家族で食事をしていた3歳の女の子がアイスクリームのふたに付いた氷を口にした。そこで異常を感じたのですぐに吐き出したが、その後も口や喉に痛みを訴え、嘔吐(おうと)などの症状を起こした。最終的には一時入院することになってしまったのだ。(TBSテレビ 8月20日)
では、なぜこのような異物混入が続いているのか。まず大前提として理解しておかなければいけないのが、メディアによって「アジェンダ設定」がなされたことも大きいということだ。
わかりやすく言えば、「大手外食チェーンの異物混入」が社会問題として大きく報じられたことで、瞬間風速的にネットやSNSの関心は高まった。その結果、平時よりも“異物混入”の被害告発が多くなされ、平時よりも積極的に拡散されてたということだ。
外食業界で働いている人はわかるが、異物混入というのは定期的に起きている。もちろん、あってはいけないことではあるが、人間が作業をしているので完全に防ぐことはできないのだ。
だが、そのように頻繁に起きている異物混入が毎度、毎度、大きな騒ぎになるわけではない。SNSでアップしてもそれほど注目を集めないことのほうが多いのだ。