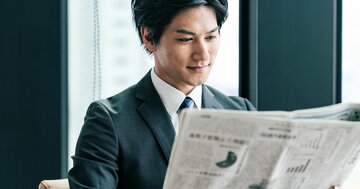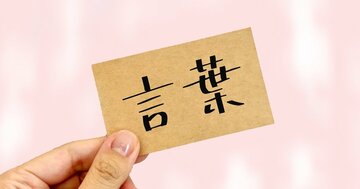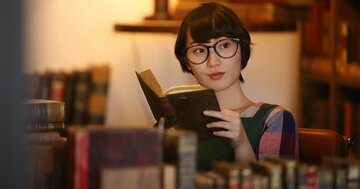ただし、ウサギだと思い込んで、何回見てもウサギにしか見えない状態だと新しい価値は見つかりません。いわば、ウサギだと思い込んでいる人に「アヒルにも見えるよ」ということを分かってもらうのが、視点を変えるということです。
柔軟に目のつけどころを変えれば、同じものでも違う価値が見つかります。
よく言われるコップの水の話もそうですね。半分まで水のあるコップを見て「あと半分しかない」と思うか「まだ半分ある」と思うか。これも視点の違いにすぎません。
自分にとって「常識」だと思っていることから、ちょっとだけ視点を変えると、違うものが見える。何かが行き詰まっている時に、視点を変えるだけで、まったく違う解決策が見えることがあります。
こうした「視点を変える」思考法は、今まで意外と重視されてこなかったように思います。現状、「仕事ができる」と評価されがちなのは、仕事をテキパキ進める「事務処理能力」「情報処理能力」の高い人です。また、そういう人が「頭がいい」という評価をされてきました。
もちろん、それも頭の良さの1つですが、それだけが「頭がいい」ということなのでしょうか。なぜなら、こうした頭の良さは、決められた仕事を進めるうえでは力を発揮するものの、壁にぶつかったり、新しいやり方を見つけなくてはならない時には、思うように活躍できないからです。
いわゆる、「課題解決」に必要とされるのは、「視点を変える」タイプの頭の良さです。
タピオカブームの終焉後も
「ゴンチャ」が生き残った理由
ビジネスの現場で「視点を変える」思考法を身につけていると、課題を解決しなくてはいけない時や壁にぶつかった時に、新たな突破口を見つけることができます。
視点を変えるやり方で成功したビジネスの実例があります。
近年、若者に人気のカフェチェーン「ゴンチャ」です。もともとは、2018年のタピオカブーム前(2015年)に台湾から日本に上陸した企業です。どの店も大行列ができるブームを巻き起こしましたが、タピオカブームの終焉にコロナ禍が加わり、客足が途絶えました。