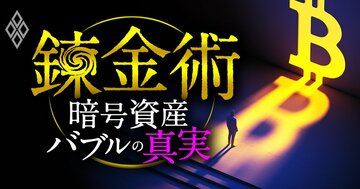Photo:Yamaguchi Haruyoshi/gettyimages
Photo:Yamaguchi Haruyoshi/gettyimages
スズキを世界的な自動車メーカーに育てた鈴木修氏は、徹底した「ケチ」で知られていた。しかし、鈴木氏本人は、自身の度を越したケチっぷりを恥じるどころか誇りにしていたようである。軽自動車という小さな市場で勝ち抜き、インドという巨大市場でも成功を収めることができた理由は、彼の哲学にある。(イトモス研究所所長 小倉健一)
ケチだけど、作業着は上質にしたワケ
鈴木修氏の「ドケチ道」は、工場の隅々にまで浸透していた。工場の蛍光灯は極力減らし、昼間は自然光を取り込んで照明代を浮かせる。部品を運ぶ際には、高低差を利用して重力で流す工夫を凝らした。
わずかな効率化を積み重ねることで、全体として大きな節約につながると信じていたからである。常に「工場にはカネが落ちている」と語り、改善の余地がどこかにあるはずだと社員に探させた。この辺り、経営の神様、稲盛和夫とも通じるものがある。
ものづくりメーカーにとって、コスト削減におけるゼロコンマ1円のレベルの切磋琢磨は当たり前のことなのであろう。
鈴木氏のケチぶりは日常の細部にも表れたわけだが、単純なコストカットではなかったようだ。
例えば、作業着だ。以前は地味で安っぽい作業着を社員に支給していたのだが、鈴木氏はあえて上質なものに変えた。
一見するとぜいたくに思えるが狙いは違った。社員がその作業着を誇りに思い、自宅から着て出勤するようになったのだ。会社に着いてから着替える時間が不要になり、無駄が消えた。更衣室のロッカーも小さくて済み、スペースの節約にもつながった。
見た目を整えることで時間とコストを削減したというわけである。