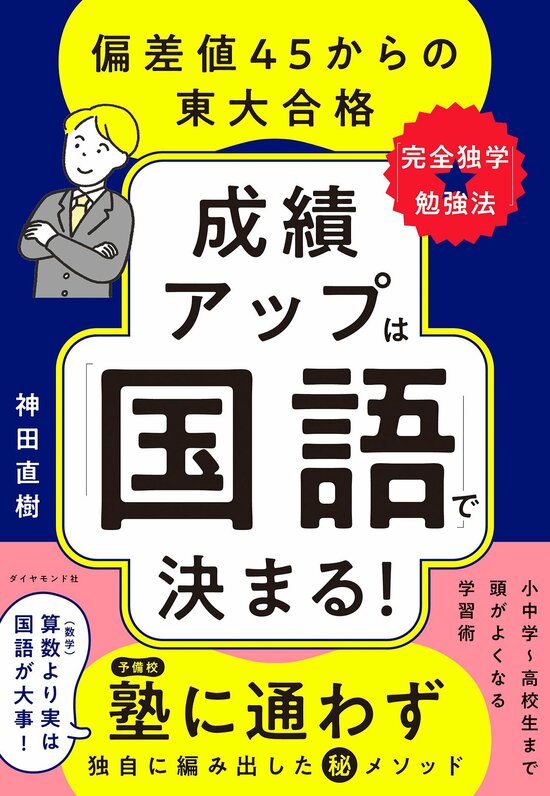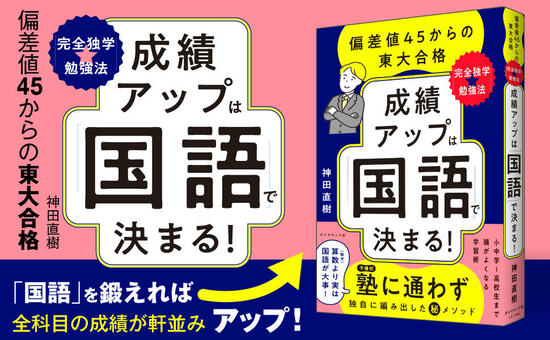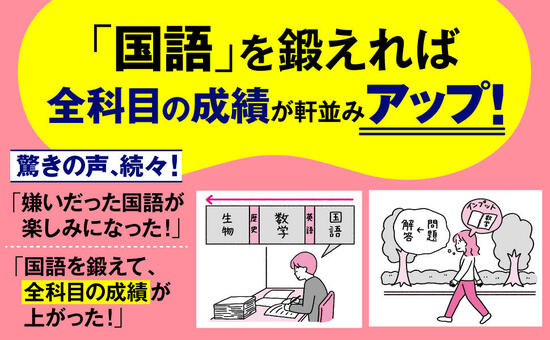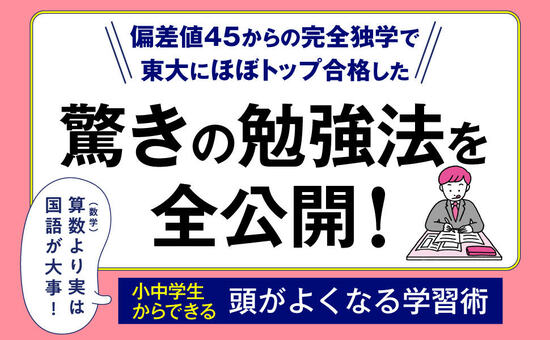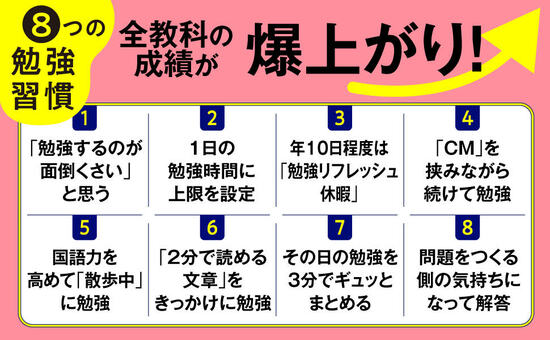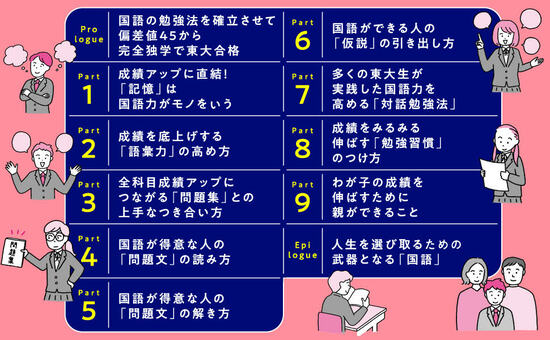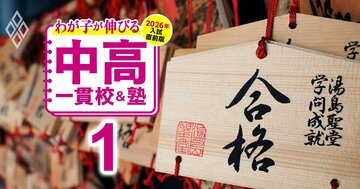東大に進学するために、高校には行かずに独学で勉強する。そんな信じられないような挑戦をして、見事東大に入学を果たした人がいる。国語特化のオンライン個別指導「ヨミサマ。」を経営する神田直樹氏だ。彼は自身の経験をもとに、『成績アップは「国語」で決まる! 偏差値45からの東大合格「完全独学★勉強法」』を上梓。さまざまな成績アップのための方法を伝授している。その中で、神田氏は「過去問を解かずに勉強するのはもったいない」と語る。なぜ、神田氏はそのように言うのだろうか。本記事では、本書の内容をもとに過去問の効果的な使い方について紹介する。(文/神代裕子、ダイヤモンド社書籍オンライン編集部)
 Photo: Adobe Stock
Photo: Adobe Stock
過去問を解かないなんてもったいない!
中学受験生に「志望校の過去問(過去に入試で出題された問題)を解いたことがありますか?」と聞くと、解いたことがある人は意外と少ないのだそうだ。
これを知って筆者は意外に思ったが、自分の記憶を辿ると、言われてみればそれほど過去問を解いたことがなかったように思う。
なぜなら、過去問にチャレンジして解けなかったらショックを受けると思ったからだ。
「もっと実力がついてからでいい」。そう考えていたように思う。
神田氏が子どもたちに訊ねてみると、筆者と同じく「いまの実力で解けないとショックを受けてしまう」「過去問は、受験の準備が最終的に整い、仕上げの段階で実力をチェックするために解きたい」などと言うそうだ。
その気持ちはわかる気がする。力不足を実感するのが怖いのだ。
しかし、神田氏は「受験を控えた学生が、過去問に目もくれないで勉強をしているのは、非常にもったいない」と語る。それはなぜだろうか。
早いほどに差がつく! 過去問の意外な効果
神田氏は、「過去問を解いた経験がなければ、学校の先生や塾の講師がくれる情報の中で、どれが入試に合格するために必要な情報なのかを自分で判断できない」と指摘する。
過去問を解いていれば、「この情報は有益だ」「この部分はそうでもない」という判断ができますから、同じ授業を聞いていても、より有益な時間を過ごせます。
過去問を解くタイミングは、早ければ早いほどいいのです。(P.95)
神田氏によると、「過去問は、現在の実力チェックのためにあるのではなく、これから自分がどれほど高い山に登るのか、そのためには何が必要で、何が足りていないのかを“可視化”するためのもの」であるという。
ここからは、神田氏が実際に東大合格に向けて、どのように過去問を利用したかを解説する。
解かずに「読むだけ」でつかむ受験の全体像
神田氏が、高校に通わず東大を受験しようと決めて真っ先にしたのは、過去問を入手することだったという。
当時、神田氏は中学3年生。もちろん東大の過去問を手に入れたからといって解けるわけではない。
この時、神田氏は問題を解いたのではなく、じっくりと読み込み、どんな問題が出ているのかを確かめたのだそうだ。
ドイツ在住でドイツ語を学ぶにはまたとない環境でしたから、ドイツ語で受験できれば少なくとも外国語では合格点を取れるはずだと思ったのです。(P.97)
他にも、日本史は暗記問題ではなく、短い文章でどう的確に表現するかという国語力が問われるタイプの問題が多く出題されることなどを知ったという。
過去問を解いて、傾向を知っておく。そのためにも「過去問は最低5年分、東大入試に関しては最終的には20年分は解いておきたいもの」と神田氏は語る。
それほどまでに徹底して過去の問題の傾向を掴んでおくことが大事なのだ。
模範解答は複数ある? 答えを比べて実力アップ
しかし、いくら過去問を解いたといっても、その年に同じ傾向の問題が出るとは限らないのではないだろうか。
出題者が裏をかいてくる可能性だって十分にある。
しかし、神田氏は「それで不安を抱く必要はない」と語る。
なぜなら、一緒に受験するライバルたちも、過去問をベースに勉強を重ねているからだ。そのため、過去問と違う毛色の問題が出された時に、苦戦を強いられるのはみんな平等なのだ。
もう一つ、神田氏は過去問を手に入れる際のポイントとして、複数の出版社や塾の過去問を比較・検討することを挙げる。
記述式の問題が大半の国語では、出版社や塾ごとに答えにバラつきがあります。同じ記述問題に対する正解が、微妙に異なっているのです。
東大の国語の過去問に対する解答は5社ほどが公開していますが、比べてみると答えは同じではありません。(P.99)
驚くべきことに、各社が公開している模範解答は、低レベルなものもあるのだという。
そのため、神田氏は「可能な限り多くの過去問の解答を見比べながら、どこが同じでどこに違いがあるのかを検討するのが有益な勉強法」と説明する。
過去問はただ問題を解くだけでなく、その解答を見比べることで学べることがあるというのは驚きだ。
解説こそ宝の山。過去問は“読む”教材
ここで、神田氏がすすめる過去問の使い方を紹介する。
1. 最初のうちは、各出版社や塾で見解が一致している問題を見つけて、自分も同じような答えが導き出せるかを考えるだけで効果的。なぜなら、答えが一致しているのであれば、それは正解に近いと考えて良いから。
2. 過去問を読み込むことに慣れたら、次は各出版社で解答の解説が微妙に異なっている問題に着目する。多くの場合、解答解説には似通った傾向があり、多数派と少数派に分かれる。そのどちらを信じるか、なぜそうなのかを比較・検討するうちに、国語力が磨かれる。
3. 過去問を解く際には、時間の制限を設けず、スマホや辞書、参考書を使ってもOK。現代の大学入試では「思考力」が問われる今、情報は自分で調べればいい。
筆者にとって過去問とは、時間内に正解を出せるようになるために解くものというイメージがあった。
しかし、解答解説を複数読み比べるなど、ただ解くよりも深い理解を得られるような使い方があることが非常に興味深い。
それくらい、受験に必要な情報が詰まっているのが過去問というわけだ。
「受験直前に」などと言わず、今すぐ過去問を手に入れたいものである。