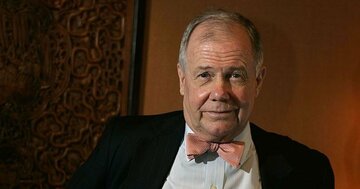ステーブルコインと仮想通貨は何が違う?
ステーブルコインとは、法定通貨に対する価値が安定したデジタルな決済手段をいう。円ステーブルコイン発行を発表したJPYC社は、19年に日本暗号資産市場株式会社として設立された。資本金は1億円、電子決済手段の発行、ブロックチェーン関連のコンサル事業などを運営する。
ステーブルコイン=JPYCの使い方は、まず、利用したい個人、法人、金融機関などが購入を申し込む。代金振り込みと引き換えに、JPYC社は顧客口座(ウォレット)にコインを振り込む。同社は、開始から3年間で1兆円分のステーブルコインの発行を目指すという。
JPYC社は1JPYCを常に1円として扱い、モノやサービスの購入、仮想通貨取引にも対応可能としている。円との等価関係の実現に、JPYC社は預金や国債を裏付け資産として保有し、金利収入を得る。
JPYCのように、価値の裏付けがあるステーブルコインを、「担保型のコイン」と呼ぶ。担保型は、短期の国債や法定通貨などを保有する。米国の金融市場では、ステーブルコイン発行業者が短期国債の保有を増やし、市場に与える影響度は上昇傾向だ。
一方、無担保型のステーブルコインもある。それはシステムが需要に合わせコイン供給量を調整する。需要が増えて価値が上昇しそうな場合、コンピューターが価値を維持するために必要なコイン量を計算して供給するシステム(アルゴリズム)を備えている。代表は「テラUSD」だった。
22年5月、テラUSDは需給バランスの調整に失敗し暴落した。テラUSDの暴落により、世界の暗号資産(仮想通貨)市場において、1日で26兆円もの価値が吹き飛んだ。テラUSDを発行したテラフォーム・ラブズは破綻した。
こうした事例の教訓から、現在は担保型、特に法定通貨を主な担保にしたステーブルコインが主流になっている。足元の時価総額は2750億ドル(約40兆円)程度、ほとんどがドル建てだ。発行額トップは「USDT」(テザー社)、2位が「USDC」(サークル社)だ。ステーブルとはいうものの、コインの価値はわずかながら変動する。この点は注意が必要だ。
誰が、いつ、いくら購入したかなどのデータは、分散型のネットワーク技術であるブロックチェーンが管理する。ブロックチェーンは、ビットコインなどの発行、取引、保有者管理などを管理する分散型元帳技術であり、暗号資産の発行、取引などの一連の経済活動を自律的に管理できる。JPYC社も、ブロックチェーンでステーブルコインの発行・管理を目指している。