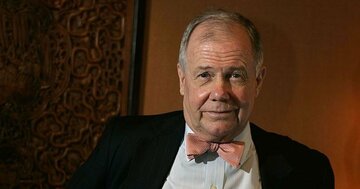写真:JPYC株式会社HPより
写真:JPYC株式会社HPより
暗号資産(仮想通貨)とは異なる、「ステーブルコイン」が9月にも日本で発行される見込みだ。2030年までに世界のステーブルコイン市場は3.7兆ドル(約540兆円)に成長するとの試算もある。日本の金融業にも相当の影響を与えるはずだ。ステーブルコインで電子マネー間の振り替え(例:SuicaからPayPayへ)も可能になるだろう。いったいどんなものか、利用者のメリットとリスクは何か。(多摩大学特別招聘教授 真壁昭夫)
いよいよ「ステーブルコイン」誕生へ
最近、海外で注目を集めている「ステーブルコイン」がわが国でも発行されるようだ。ステーブルコインとは、円やドルなどの「法定通貨」や短期の国債などを担保に発行し、価格が安定(ステーブル)するよう設計された電子決済手段。暗号資産(仮想通貨)とは異なるものである。
米国ではステーブルコインを発行する企業が急増中だ。中国も人民元に連動するステーブルコイン発行を検討中だ。2023年6月に、ステーブルコインの根拠法規である改正資金決済法が施行されてから約2年がたつ。わが国でも、ようやくステーブルコイン発行にめどがついたようだ。
8月18日、金融庁はフィンテック企業のJPYC社を資金移動業者(資金送金を行う銀行以外の事業者)に登録した。9月にも、同社は円と1:1で交換できるステーブルコイン「JPYC」を発行する計画だ。実現すれば、国内で初となる。
ステーブルコイン発行の主な目的は、資金決済のコストを削減し経済の効率性を高めることだ。米国では、著名フィンテック企業のサークルなど、非金融企業がステーブルコイン事業を急拡大している。香港のOSLグループなどもわが国に参入した。わが国の現金利用割合はいまだ高いこともあり、ステーブルコインによる決済の効率化のメリットは大きいとみられる。
ただしステーブルコインには、犯罪に使われるリスクや利用者保護の課題もある。当面は、JPYC社が安心・安全な利用環境を整備できるか否かに注目したい。そして中長期的には、わが国の金融システムのデジタル化に相当の影響を与えることになるはずだ。
米大手金融機関の試算の一つによると、30年までに世界のステーブルコイン市場は3.7兆ドル(約540兆円)に成長するという。わが国は、そうした変化に対応できるのか。なぜなら既存の銀行の必要性が低下するかもしれないからだ。