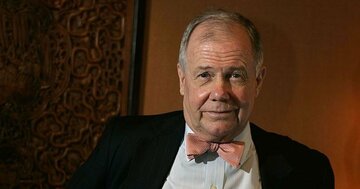JPYCなどステーブルコインの大きなメリット
ステーブルコインの大きなメリットは、資金決済を中心に経済活動の効率性が向上することだ。JPYC社によると、同社のステーブルコインを使うことで、1円から世界中に最短数秒で送金が完了する。同社は今後、ブロックチェーンの送金コストが1円以下になると予想している。重要なポイントは、ブロックチェーンの有用性・効率性である。
改めて言うと、お金(法定通貨)の利用にはコストがかかる。現金を保管するのに金庫が必要だし、輸送するには専用車両、訓練を受けた人員も必要だ。銀行はATMや支店網の運営コストを負担してきたが、わが国では人口減少もあって難しくなりつつある。さらに、サーバーを置く建物(不動産)の取得費用、システム運営のコストも重い。
世界銀行の推計によると、送金コストの世界平均は「金額の6.49%」とのこと。わが国は平均よりかなり高く、邦銀が国際銀行間通信協会(Swift)を使って200ドルを送金すると、そのコストは17.5%(13~19年平均)かかる。米国の6%程度を大きく上回る。
ステーブルコインの発行・管理に使うブロックチェーンは、異なる端末で同じデータをほぼ同時に、しかも自律的に共有する。ブロックチェーンは、省人化、サーバーの設置場所、管理コスト削減に有効だ。それが資金決済コストの低下を可能にする。
こうしたメリットを享受しドル基軸体制を維持するため、トランプ政権は関連法案を制定した。6月に上院が可決したGENIUS法(Guiding and Establishing National Innovation for U.S. Stablecoins Act)が代表例だ。
米国では、サークルなどの大手ステーブルコイン発行業者に加え、ウォルマートやアマゾンなど一般企業もドル連動のステーブルコイン導入を検討している。コスト削減に加え、決済スピードも速い。
クレジットカードの決済は、多くのケースで買い物をした翌月に行うことが多い。ステーブルコインだと、事業者は瞬時に受け取る資金をすぐ使える。ステーブルコインで電子マネー間の振り替え(例:SuicaからPayPayへ)も可能になるだろう。
ステーブルコインは、企業の資金効率化にとどまらず、海外労働者の本国送金コストの低減にも有効だ。わが国ではSBIホールディングスが、米サークルやリップルと提携し、ドルのステーブルコインの国内利用に取り組んでいる。