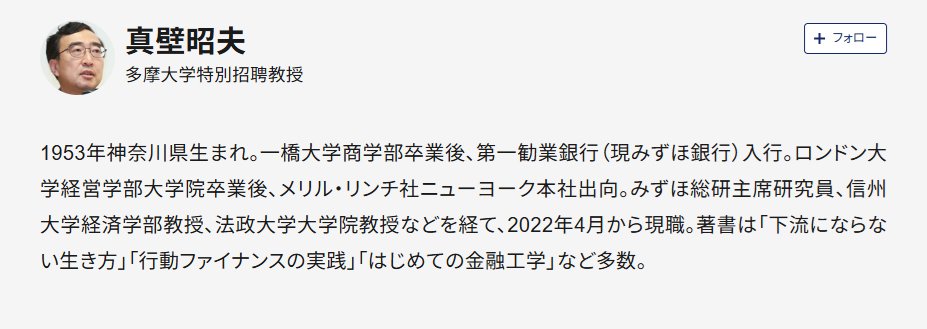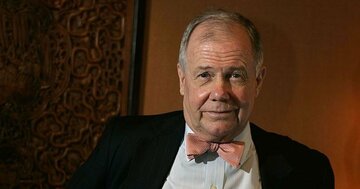ステーブルコインの無視できないリスクと課題
一方、ステーブルコインには無視できないリスクや課題もある。米国のGENIUS法をはじめ、主要先進国の関連法規制を拡充すべきとの指摘は多い。もし、銀行取り付け騒ぎのような事態(バンク・ランになぞらえステーブルコイン・ランと呼ばれる)が起きた際、その対応について現時点では明確になっていない。
仮に、大手のステーブルコイン発行業者の経営不安が高まると、ステーブルコインの売りは増えるはずだ。売りが買いを上回れば、価値が下落するリスクは高い。内外で取引される他のステーブルコインにも売り圧力は波及し、国境をまたいだ金融システム不安が起きることも考えられる。
その場合、消費者や企業経営者の心理は悪化する。ステーブルコイン発行業者の経営破綻が、多くの投資家のリスクオフにつながることも想定される。そうした潜在的リスクにどう対応するか、政策連携、ステーブルコイン発行業者の資本規制、顧客資産の分別管理が急務である。
また、ステーブルコインが犯罪に使われる恐れもある。特に、テロ組織によるマネーロンダリング(資金洗浄)の撲滅は重要だ。資金移動業者のウォレットから、ステーブルコインが盗まれるリスクにどう対応するかも明確ではない。
JPYC社に求められるのは、リスクと課題に迅速に対応し、安心・安全なステーブルコインの利用環境を確立することだ。同社は内外企業との利用、システム開発などのネットワークを拡充することになるだろう。
わが国は、変化に対応できるのか。JPYCの発行をきっかけに、大手金融機関やフィンテック企業が連携し、より安定した事業基盤を整備することが求められる。そのためにも、JPYC社がどのように内外企業と協業体制を進めるかに注目したい。米欧や中国などでステーブルコインが増える一方、わが国で思ったように利用が広まらないと、金融分野のデジタル後進国ぶりはこれまでに増して深刻になることが懸念される。