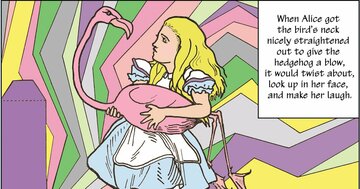そしてそのラテン語は、中世ヨーロッパでは文法のみならず「神秘学」「オカルト研究」をも意味するようになり、中世後期にこの単語がラテン語から英語に借用されてgramereになり、それが近代英語のgrammarになった。そこからさらに「魔術」「降霊術」を表わすgramaryeという派生語が生じた。
このような連想から、18世紀初頭にスコットランド方言としてglamour(「魔法」「呪文」の意)が発生し、それから意味も使われる地域も広がって「魅惑」として英語に定着したのであった――この語を広めたのはスコットランドの国民的作家ウォルター・スコットだったらしい。魔法の呪文を唱えるごとく相手を魅了する、ということである。
20世紀になるとそれが「性的魅力」の意味に特化され、1930年代にはglamour boyというフレーズが成立し、主に英国空軍の若い飛行士を指して用いられた。少し遅れてglamour girlが若いファッション・モデルや女優に対して使われるようになったが、日本語の「グラマー」と違って豊満な体型という含みはない。
「トランジスター・グラマー」は
語源学的には大きな間違い?
1950年代末期に日本で「トランジスター・グラマー」が流行語になった。これは小柄で「グラマーな」女性を指して言う和製英語らしいのだが、語源学的には大きく間違っている。「トランジスター・グラマー」は「トランジスター・ラジオ」からの連想で「小型のグラマー(な体型の人)」を意味するという。
だが、「トランジスター」は「小型の」ではない――トランジスター・ラジオは確かに、それ以前の真空管ラジオと比べたら「小型のラジオ」ではあるが。「トランジスター」(transistor)はtransfer(「移動する/移動させる」――原義は「別な場所へ運ぶ」)とresistor(「抵抗する者」――原義は「反対向きに立つ者」――から転じて「抵抗器」)の「鞄語」で、「半導体を用いた回路素子」を意味する(初出は1948年、原理が発明されたのはその前年)。
世界初のトランジスター・ラジオが1954年に米国で発売され、翌年には日本でも製造されるようになったのだが(関係ないが『ひよっこ』というドラマで、私の好きな女優の一人である有村架純扮する主人公みね子らは一時期、トランジスター・ラジオを組み立てる工場で働いていた)、このあたりで「トランジスター・ラジオ」が「小型ラジオ」と誤解されたらしい。この誤解から「トランジスター・グラマー」という流行語が発生したのである。