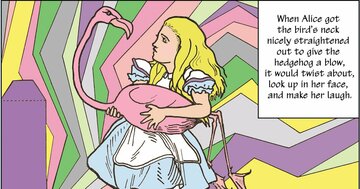例えば18世紀英国小説を代表するヘンリー・フィールディングの『トム・ジョウンズ』の原題はThe History of Tom Jones,a Foundlingであるし、日本語では「歴史画」と訳されることが多い絵画のジャンルhistory painting(神話や古典文学を題材にした絵)も、「物語画」という訳語の方が正確であろう。
語源学的にも興味深い
日本のソウルフード「醤油」
「塩」(salt)と「ソース」(sauce)も実は同語源だ。塩は古英語でもsalt、ドイツ語ではSalzだが、さらに遡ればラテン語sal(形容詞形はsalsus)である。一方sauceはラテン語のsalsusが俗ラテン語(古代ローマの民衆の口語)でsalsaになり、それがフランス語に借用されてsauceになって、14世紀頃に英語に借用された。
そしてこの俗ラテン語salsaは、19世紀中葉にもう一度、今度はスペイン語経由で英語に借用され、メキシコ料理のソースを指して使われるようになった。特にこのメキシコのソースについては、日本語でも英語でも「サルサ・ソース」とよく言うが、それは単に「ソース」と2回言っているに過ぎない。
目玉焼きには醤油かソースか、という問題は議論し始めると白熱しやすい。私は断然醤油派だ――もっとも私は筋金入りの醤油好きなので、揚げ物全般もお好み焼きもタコ焼きも醤油だし、何なら焼きそばも醤油で味付けしたいとさえ思う。そして醤油は調味料として優れているだけでなく、語源学的にも実に興味深い。
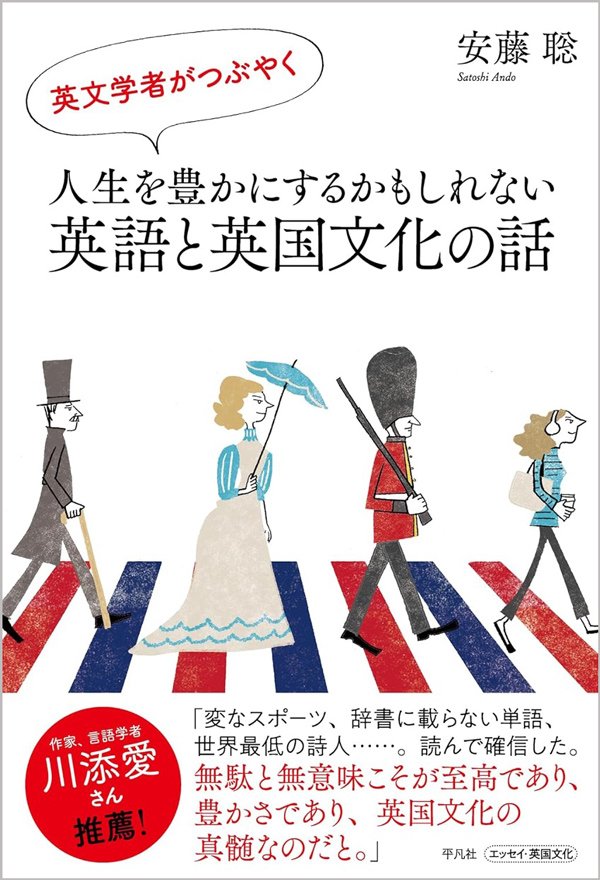 『英文学者がつぶやく 人生を豊かにするかもしれない英語と英国文化の話』(安藤 聡、平凡社)
『英文学者がつぶやく 人生を豊かにするかもしれない英語と英国文化の話』(安藤 聡、平凡社)
醤油を英語でsoyまたはsoy sauceと言い、大豆(soy beans)を主な原材料とするからソイ・ソースだと思われがちだが実は逆で、soyの語源は日本語の「醤油」なのである。ついでながら、吃逆が止まらない人に唐突に「醤油の原料は?」と大声で問いかけると、たいてい止まる。「豆腐の原料は?」でもよい。いずれにせよ答えは同じだ。
「醤油」は17世紀末にオランダ語経由で英語に借用されてsoyまたはsoyaとなった。1660年代から90年代初頭にかけて、長崎の出島からオランダ東インド会社に醤油が輸出され、これが17世紀末に英国に伝わったのであろう。語源的にはsoyよりもsoyaの方が古く、soyaの語尾の母音が脱落してsoyになったと推測される。現在ではsoyaが「大豆」、soyが「醤油」の意味で使われることが多い。