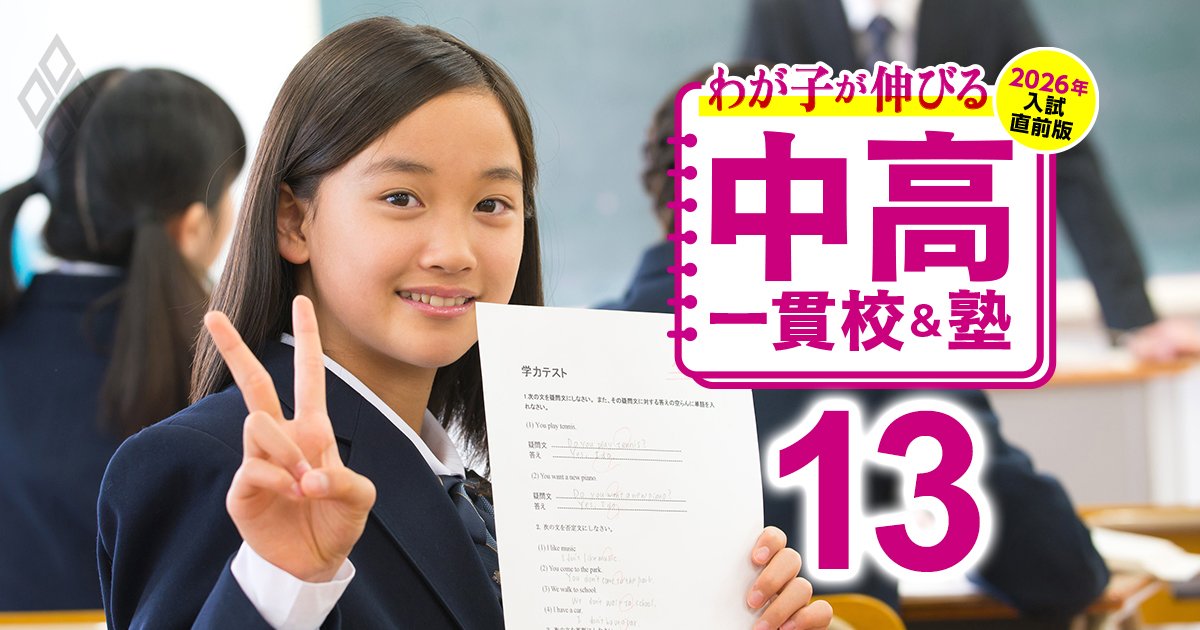 Photo:PIXTA
Photo:PIXTA
「中堅校」人気が加速している。中高の6年間を通じて「わが子が伸びる」という視点で学校選びをする保護者が増加しているからだ。とはいえ、中堅校は御三家や早慶付属と比較して情報が少なく、学校選びが難しい。そこで特集『わが子が伸びる中高一貫校&塾 2026年入試直前版』の#13ではプロ5人が厳選した「偏差値30台、40台から狙えるお薦めの23校」を一挙に紹介する。中堅校は改革意識が強く、「面倒見の良い」学校が多い。学校のタイプも共学、別学、大学付属、国際系…などがそろうので本命校候補としても併願校候補としてもチェックしてほしい。(ダイヤモンド編集部 篭島裕亮)
改革意識が高い中堅校が人気に
総合型選抜を意識した取り組みも
「学校選びがピラミッド型から八ヶ岳型に変わってきている」(森上教育研究所代表の森上展安氏)――。
史上最高レベルの激戦となる2026年2月の中学入試だが、その人気をけん引するのが「中堅校」だ。男女御三家など難関校の志望者が減少傾向にある一方、ここ数年の大きなトレンドとして、偏差値的には中位や下位の学校で志願者を伸ばすところが増えている。
四谷大塚情報本部本部長の岩崎隆義氏は「保護者の価値観が多様化している。ひと昔前だったら、小学6年生になると受験勉強のために習い事を整理するケースが多かったが、今は継続する家庭も少なくない。勉強以外の物差しを持つ家庭が増えたことで中学受験の裾野が広がっている」と指摘する。
実際、各種模試の学校別志望者動向を見ると、偏差値30台から50台の学校の躍進が目立つ。26年2月入試では中堅校人気がさらに加速するといえるだろう。
進学レーダー編集長兼日能研進学情報センター長の石井史子氏は下記のように分析する。
「10年前、20年前のようにミッション校、男子校・女子校などにこだわるのではなく、中身で選びたいという家庭が増えている。偏差値だけで選ぶ家庭も減り、保護者のこだわりが多様になっている。氷河期世代の保護者が多いため、“この学校に行ったら安心”という過去の評価に惑わされたくないということもあるのではないか」(石井氏)
近年は受験校を決める前に学校説明会だけでなく、文化祭などを通じて学校を見学することが当たり前になっている。その際、保護者がチェックするのは進学実績や学習指導だけではない。行事や部活、さらには生徒の様子を見て「わが子の興味関心を伸ばせるか」「中高の6年間が楽しく充実した時間になるか」を判断しているのだ。
少子化が加速していることもあり、中堅校ほど生き残りを懸けた改革への意識は高い。SNSでの外部発信も積極的だ。
「大学入試で主流になりつつある総合型選抜を意識した取り組みについては、中堅校の方が進んでいるケースが多い。特にグローバル教育とSTEAM教育を両立させる学校が人気になっている。また、単に面倒見がいいだけでなく、生徒の学習へのモチベーションを上げる仕掛けを重視して、失敗してもいいからチャレンジさせるような生徒の主体性を尊重する学校の人気が上がる傾向がある」(首都圏模試センター教育研究所長の北一成氏)
一方、これだけ注目度が高まっているにもかかわらず、中堅校の情報は御三家や早慶付属などの難関校と比較すると少ない。中堅校は学校の数も多いだけに、わが子に合った学校を選ぶのが難しいのが現状だ。
そこで、次ページでは識者5人が厳選した中堅校23校を推奨理由と共に一挙に紹介する。偏差値は日能研や四谷大塚の偏差値で30台から50前後までの学校群だが、各校とも改革に着手しており、「6年後の出口」は現在の実績と様変わりする可能性もある。
学校のタイプも「男女別学と共学」「進学校と外部進学も可能な大学付属校」「伝統校と新興校」「自由型と面倒見のいい学校」など選択の軸が複数あるので、わが子に最適な学校を選びやすいはずだ。私学の環境には興味があるが、「わが子に合ったペースで中学受験に挑みたい」という家庭も注目してほしい。
多くの識者、中学受験を経験した保護者が述べるように「波乱があるのが中学受験」である。早い段階で「わが子に通ってほしい学校」を多く用意しておくことは、受験直前期の安心感にもつながる。本命校候補としてはもちろん、併願校候補としてもぜひチェックしてほしい。
わが子が伸びる中堅校はどこか。次ページでは四谷大塚・岩崎隆義氏、日能研・石井史子氏、森上教育研究所・森上展安氏、首都圏模試センター・北一成氏、オンライン家庭教師・田中則行氏が注目の中堅校23校を一挙に紹介する。







