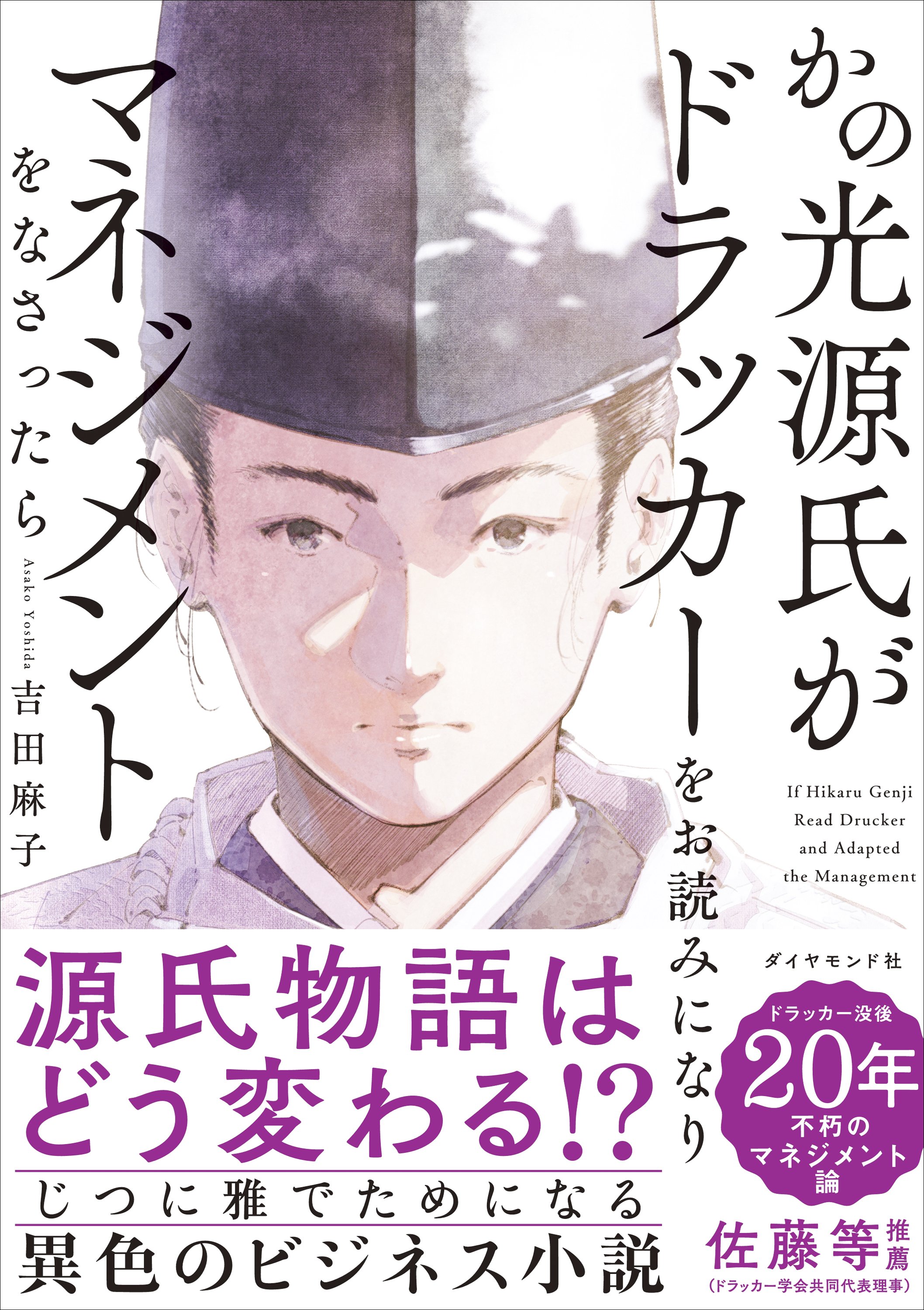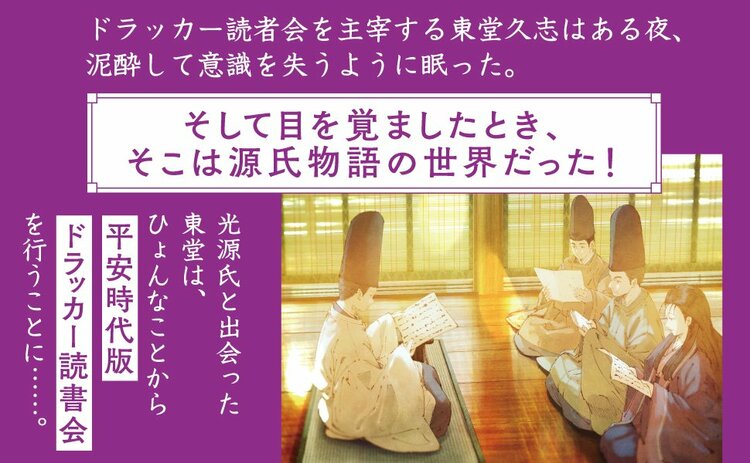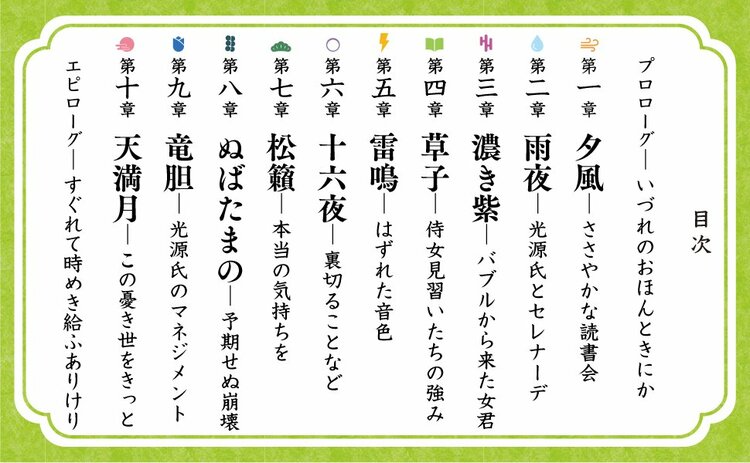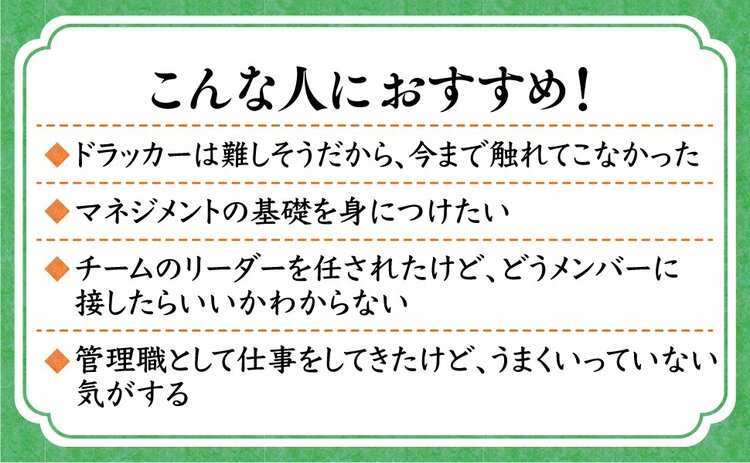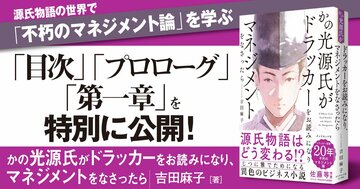働く者を取り巻く四つの現実
【第一の現実】:同僚や上司の「ちょっといい?」が一番の時間泥棒
「第一の現実は、時間がすべて他人にとられてしまうことである」
組織にいると、誰もが時間泥棒になりうる状態が起こります。
「一瞬、時間いいかな?」と言われて「少しなら」と思っても実際にはそれが度重なることによって膨大な時間を取られることになってしまうのは、誰もが経験していることかと思います。
【第二の現実】:本業を妨げる雑務の洪水
「第二に、日常業務に取り囲まれていることがある」
真になすべきことのためにすべての時間を使うのは困難なことです。
看護師が自分の専門分野にだけ集中する、教師が授業のことだけに専念する、という本業以外に電話の応対や備品の発注、日誌の記入や、同僚や後輩の相談など、実にさまざまな日常の仕事に取り囲まれています。
【第三の現実】:成果は一人では出せず、他者依存が避けられない
「第三の現実が、組織で働いていることである」
自らが組織の一員であるということは、組織の中の他の誰かが自分の貢献を利用してくれるときにのみ、成果をあげることができるという現実があります。
「自分さえよければいい」ということにはならないため、いかにして他の人の仕事に貢献できるかを考えなければなりません。そのためには情報提供やコミュニケーションなどあらゆる努力が必要となるでしょう。
【第四の現実】:社内のことばかり見て、外の成果を見失う
「そして最後に、組織の内なる世界にいるという現実がある」
組織の内部を直接的に見ていることになるため、たとえ組織の外を見たとしてもそこには何らかのバイアスがかかってしまいます。
ドラッカーはこの節で、「特に重要なこととして、組織の中に成果は存在しない。すべての成果は外にある」といっています。にもかかわらず、内部の課題や急ぎの案件に引き込まれ、成果の源泉である外に目を向けることを忘れがちなのです。
では、時間を創り出すにはどうする?
さて、そんな“時間泥棒”に囲まれた環境において、真になすべきことのために時間を創り出すにはどうしたらよいでしょうか。
ドラッカーは『経営者の条件』の『第二章 汝の時間を知れ』の中で、成果を上げるための時間管理の基本として3つのステップを紹介しています。
「時間を記録する、整理する、まとめるの三段階にわたるプロセスが、成果をあげるための時間管理の基本となる」
(1) 時間を記録する
「知識労働者が成果をあげるための第一歩は、実際の時間の使い方を記録することである」…Excelでも手書きでもスマホアプリでもよいので、リアルタイムで自分の時間の使い方の記録を取っていきます。
(2) 時間を整理する
「時間を浪費する非生産的な活動を見つけ、排除していくことである」
時間の記録を見返し、自分がやっている各作業や活動について、時間の浪費であれば「やめる」、他の人でもできることであれば後輩に譲るなど「人に任せる」、会議の過剰や情報伝達不足など「組織構造の間違いがあれば正す」というように整理していきます。
(3) 時間をまとめる
「成果をあげるには自由に使える時間を大きくまとめる必要がある」
企画書を作る、原稿を書く、などある程度のサイズのある業務は10~15分程度の時間の切れ端を積み重ねるよりも連続した数時間の方が質の高い仕事ができます。
これらのことを実践することによって、時間に余白が生まれ、本当にやるべき「自分の仕事」を進めていくことができるようになっていきます。
では、あなたが“時間泥棒”から解放されるために、すぐに実践できる4つのチェックポイントを紹介します。
✔ 自分の時間の使い方を記録したか?
✔ 無駄な会議や繰り返しの作業を減らせないか見直したか?
✔ 集中したい仕事に、最低でも90分の「塊時間」を確保したか?
✔「本当にやるべき仕事」を、毎朝いちばんに確認したか?
時間泥棒は、あなたの背後でこっそり働き続けています。
だからこそ「時間を記録する」「整理する」「まとめる」という習慣を持つことが、未来の自分を守る最大の武器です。
“時間泥棒”に気づいた瞬間が、行動の始まりです。
今日から、自分の時間を守り抜き、真に成果につながる仕事へ一歩を踏み出しましょう。