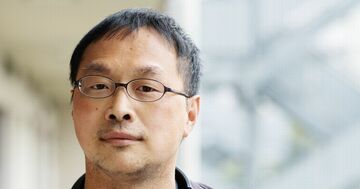今後、鑑賞料金がどんどん上がっていくと起こること
話を鑑賞料金に戻そう。このまま鑑賞料金がどんどん上がっていくなら、今後「確実に面白い」ことが保証されていない映画は、夏祭りの露店で売られている「具がほとんどないのに600円もする焼きそば」や「4、5切れを串刺しにしただけで1本1000円もする牛串」のような存在になっていくだろう。
その心は、料理の「質」ではなく料理を食べる「雰囲気」にその金額を払える人だけが、600円なり1000円なりを払うということ。もし美味しかったら、かなりラッキーだ。同じように、映画の内容ではなく映画館という場所で映画を観る体験にその金額を払える人だけが、2200円を払う。もし面白かったら、これまたかなりラッキーだ。
ところで夏祭りといえば、露店で「仙台牛タン800円」と称して売られていたものが豚タンだった、というXの投稿が先日話題になっていた。投稿者が店の人に確認すると、半笑いで「豚です」と答えたという。
言ってしまえば、昔の映画宣伝はそういうものだった。予告編で超大作SFと煽っていたので観に行ったらしょっぱいB級ホラーだった、ポスターに超巨大モンスターが描かれていたが本編には一切登場していなかった、といった話は枚挙にいとまがない。「怪奇!蛇喰い女!」と謳う見世物小屋に木戸銭を払って入ってみたら、半裸の老女が何だかわからない干物を食いちぎっていた……と同じ類いである(筆者が体験した実話)。
それでも昔は、笑って「ダマされたぁ!」と流せる程度には、人々の懐に余裕があった。しかし今はない。どんなストーリーで、どこが見せ場で、何に感動するのかを、あらかじめ具体的かつ詳細にわたって説明を受け、コスパの高さに納得できなければ、人々はビタ一文払わない。無論、羊頭狗肉は絶対NG。看板に偽りがあれば即炎上となる。
今や「騙されたぁ!」と笑って流せるのは、クリック・タップしたところで懐(ふところ)は痛まない「見出しが盛られたウェブ記事」くらいのものか。否、それすら笑って流せない人のほうが、今は多いのかもしれない。
「懐は痛まなかったが、時間を返せ」
懐にも心にも余裕のないご時世である。