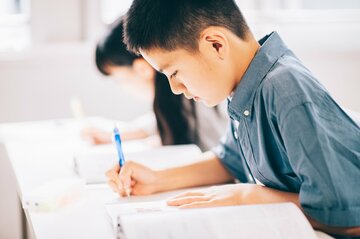写真はイメージです Photo:PIXTA
写真はイメージです Photo:PIXTA
中学受験の併願校選びは、合否を大きく左右する。SNSの体験談や噂に惑わされるのではなく、塾が持つ入試分析や最新情報をどう使いこなすかが鍵になる。「全落ち」を避ける備えや、逆転合格をつかむ生徒の共通点などを挙げて、冬の本番に向けた戦い方を提案する。(国語専門塾の中学受験PREX代表、教育コンサルタント・学習アドバイザー 渋田隆之)
併願校選びで活用したい塾のノウハウとは
併願校について前回に続いて取り上げます。
併願校選びをする際に頼りになるのは通っている塾の先生。ただし、いくら先生でも首都圏に300校以上ある学校の全てに精通するのは難しいことです。そこで保護者の方は「手放しにおすすめ学校を紹介してもらう」のではなく、「入試問題を分析してもらう」と視点を変えて、塾のノウハウを活用することを提案します。
具体的には、意識したいのは以下の2点です。
(1) 塾の先生に入試問題との相性を見てもらう
学校の顔と言われる入試問題には、“こういう生徒に入学してほしい”という意図が明確に現れています。「理科の授業で実験観察を重視する学校は、実験を切り口にした問題が多い」「中学生のうちから論文を書かせる学校は、記述式の問題が多い」などが良く言われるところです。
つまり、入試問題との相性が良い学校は、少なくとも授業を受ける際にミスマッチを感じることが少ないと言えるでしょう。塾の先生は、過去問分析のスペシャリストなので、本人の学力特性、教科特性と合った学校をいくつかピックアップしてもらうと良いでしょう。
(2) 受験校のチャートの作り方
受験校のチャートとは、「2月1日の午前にA中、午後にB中を受験して、もしB中の合格が判明したら、2日はC中を受ける……」といった受験パターンのことを指します。
こうしたチャートを作る際、まずはSNSなどの「先輩保護者の体験談は、併願作戦には使えない」と割り切りましょう。
ほんの数年であっても当時から時間がたっている体験談は、現実と大きくかけ離れていることがあります。受験情報は「生もの」であり、賞味期限は短いものです。
ある規模以上の塾であれば、秋の時点で、他塾も含めての模試の志望校動向を入手できています。最新情報に基づいたアドバイスについては、専門家にしかできません。ここは「餅は餅屋」です。